相続順位は、相続が発生した際に注目される制度です。
相続順位によって相続する財産の割合にも影響があります。
本記事では相続順位を含む遺産相続について以下の点を中心にご紹介します。
- 相続順位とは
- 離婚相手との子に相続権はあるのか
- 法定相続人がいない場合、遺産はどうなるのか
相続人を決める仕組みについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続順位とは

相続とは、財産や資産が亡くなった方から法的に引き継がれる手続きです。
相続の手続きには、相続順位という制度があります。
相続順位は、誰が遺産を受け継ぐ権利があるかを決定するルールです。
相続順位は、亡くなった方の親族関係に基づいて決まります。

配偶者がいる場合、最初に配偶者が相続権を持ち、遺産の一部または全部を受け取る権利があります。
配偶者がいない場合、亡くなった方の子供たち(直系の親)が相続権を持ちます。
子供たちが遺産の相続をする場合、子供たちの中で平等に分配されることが一般的です。
配偶者も子供もいない場合、兄弟姉妹が相続権を持ちます。
故人の兄弟姉妹が相続を行う場合、兄弟姉妹の中で平等に分配されます。
相続順位は、法律に基づいて明確に規定されています。
ただし、特殊な状況や遺言がある場合、順位が変わることもあります。
遺産相続は、亡くなった方の財産をどのように分配するかを決定する重要なプロセスです。 その中心的な要素の一つが「遺産相続順位」です。 この順位は、誰が遺産を相続する権利を持つか、そしてその順序は何かを決定します。 本記事では、遺[…]
配偶者以外は相続順位に沿って決定

相続において、財産を引き継ぐ権利を誰が持つのかというのは、相続順位によって決められています。
日本の民法において、相続順位は第1順位から第3順位まで設けられており、第4順位は存在しません。
相続順位の中で、特に注目すべきは第1順位に位置づけられている配偶者です。
民法によれば、日本の相続法では配偶者が最優先で相続人となります。
つまり、亡くなった方の配偶者は、必ず相続人の権利を有します。
この法的定めは、夫婦間の結びつきを尊重し、配偶者が遺産を引き継ぐ権利を確保するためのものです。
第1順位の配偶者の次に、相続順位第2位には直系の親や子供などが位置します。
配偶者がいない場合、亡くなった方の子供たちが相続権を持つことになります。
直系の親族関係が重要であり、子供たちの中で遺産が平等に分配されることが一般的です。
相続順位には制約も存在します。
例えば、相続順位第2位の相続人は、第1順位の相続人である配偶者が存命の場合、相続人になることはできません。
また、上位の順位にいる相続人がすでに亡くなっている場合や相続放棄をした場合、下位の順位の相続人が権利を行使できるようになります。
相続順位の早見表
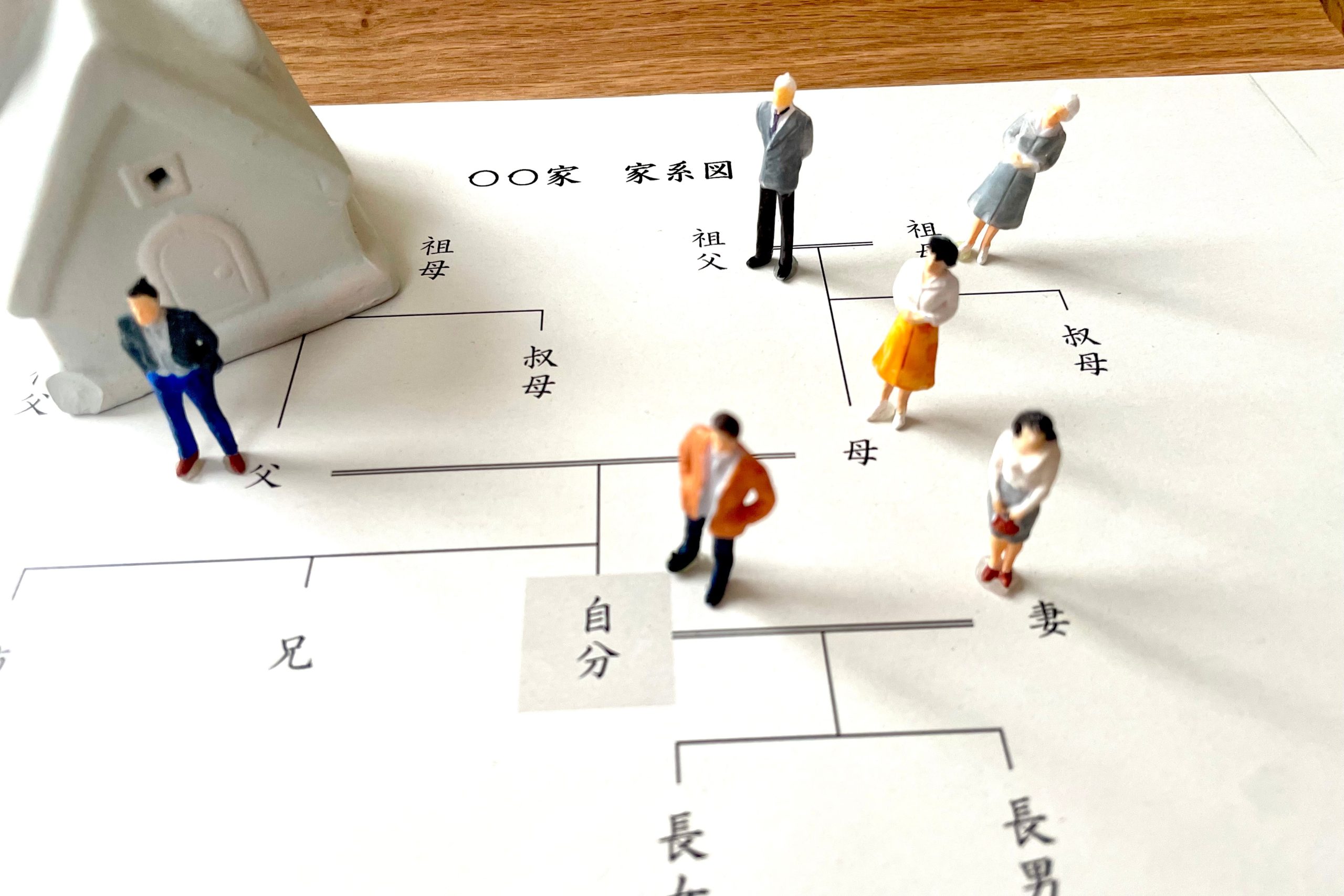
血族における相続にも優先順位が設定されており、先の順位にいる血族相続人が相続権を行使している場合、後の順位の血族相続人には権利が及びません。
以下は、血族相続人の優先順位の一般的なルールです。
| 相続順位 | 被相続人との関係 | 代襲相続の有無 |
| 最優先 | 配偶者 | ー |
| 第一順位 | 子供 | あり(再代襲もあり) |
| 第二順位 | 親(最も親等が近い直系尊属) | ー |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 | あり(再代襲はなし) |
法定相続分とは

相続において、遺産の分割は民法によって厳格に規定されており、法定相続分と呼ばれる相続割合が決められています。
法定相続分は、遺産分割協議や調停、家庭裁判所による遺産分割審判の際の基準となります。
以下では、配偶者の有無に応じて法定相続分とその割合について説明します。
配偶者がいる場合
配偶者がいる場合、法定相続における基本的な相続割合は以下の通りです。
- 配偶者と子どもが相続人の場合:配偶者が2分の1、子どもが2分の1
- 配偶者と親が相続人の場合:配偶者が3分の2、親が3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
同じ順位に複数の相続人がいる場合、相続分は人数で均等割になります。
例えば、配偶者と2人の子どもが相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもたちがそれぞれ4分の1の相続分を受け取ります。
養子、前婚の子ども、または認知された子どもは、亡くなった時点での家族の子どもと同じく、相続権が認められます。
配偶者がいない場合
配偶者がいない場合、相続人の人数に応じて均等割が適用されます。
たとえば、3人の子どもが相続人となる場合、各子どもの相続分は全体の3分の1になります。
ただし、代襲相続が適用される場合、必ずしも均等に分割されるわけではありません。
代襲相続については以下で詳しく説明します。

複雑な相続順位のケース

遺産相続において、法定相続分や相続順位には一般的な原則がありますが、実際の相続ではさまざまな複雑な状況が発生することがあります。
以下では、相続順位が問題となりやすいイレギュラーなケースについてわかりやすく説明します。
代襲相続(孫の相続)
代襲相続は、亡くなった人に子供と孫がいる場合で、相続発生時に子供が既に亡くなっている場合に発生します。
相続発生時に子供が既に亡くなっている場合、孫が代襲相続人となり、法定相続分の原則に従って相続権を行使します。
つまり、孫は亡くなった人の子供が生きていた場合と同じ相続順位で、第1順位の相続人となります。
同様に、亡くなった人に子供、孫、ひ孫がいる場合で、相続発生時に子供と孫が既に亡くなっている場合には、ひ孫が再代襲相続人となります。
このケースでは、再代襲相続人(ひ孫)も法定相続分の原則に従って相続権を行使します。
代襲相続の権利は、兄弟姉妹の子(亡くなった人から見て甥っ子、姪っ子)にも認められます。
例えば、亡くなった人の子供がいない場合で、兄弟姉妹が相続人として指定されていた場合、兄弟姉妹の子どもたちが代襲相続人となり、相続権を行使します。
相続に関連して、相続人が相続放棄をする場合があります。
相続放棄をした相続人は、最初から相続に関する権利を持たないものとして扱われます。
そのため、相続放棄をした人の子(亡くなった人から見て孫)も、最初から相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄は、個人の意思に基づくものであり、相続にかかわりたくない場合に選択されることがあります。
相続欠格や廃除といった場合も、代襲相続が発生することがあります。
相続欠格とは、亡くなった方を暴行したり、殺害にかかわったりした場合に相続人となる権利を失うことを指し、廃除とは遺言によって相続人となる権利を失うことです。
相続欠格や廃除に該当する人の子(亡くなった人から見て孫)がいた場合には、代襲相続が発生し、相続権を行使します。
遺産相続において、これらのイレギュラーなケースは法的に複雑です。
そのため、相続に関する問題が発生した場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
個別のケースに応じて適切な対策を講じることが、円滑な遺産分割につながります。
代襲相続以外の孫の相続
遺産相続において、孫に遺産を相続させる方法は代襲相続以外にもいくつか存在します。
こうした方法を活用することで、財産を孫世代に受け継がせることが可能です。
以下、孫に遺産相続をさせる方法とそのメリット・デメリットについて詳しく説明します。
遺言書で孫に相続させる
遺言書を作成することで、孫に遺産を相続させることができます。
遺言書には相続人や財産の分配方法を明示でき、孫を直接指定が可能です。
遺言書を作成する際には、法的な要件や手続きに注意が必要ですが、孫への財産譲渡を実現する手段として有効です。
孫を養子にする
もう一つの方法は、孫を養子にすることです。
養子縁組を通じて、法的な親子関係が成立し、孫が法的な相続人となります。
養子縁組には一定の手続きと条件が必要ですが、孫への相続権付与が可能です。
生前贈与を行う
また、生前に贈与を行うことで、孫に財産を譲渡できます。
生前贈与は、相続税の対象になる場合がありますが、贈与税の控除や非課税枠を利用することで、税金を軽減できる場合もあります。
しかし、子供を飛ばして孫に直接相続させる場合、相続税の金額が20%加算されるというデメリットが存在します。
ただし、親から子供への相続とその後の子供から孫への相続という2回の相続を経る場合、相続税も2回分支払う必要があるため、最終的には相続税の負担が小さくなることもある点に注意が必要です。
胎児の相続
遺産相続において、胎児が存在するケースは特別な状況であり、法的な取り決めが必要です。
以下では、胎児がいる場合の相続について詳しく説明します。
相続が発生した時点でまだ生まれていない胎児は、すでに生まれている子供と同じように扱われます。
つまり、胎児が将来生まれることを前提に、相続人として考慮されます。
この場合、母親と胎児が相続人となり、通常は第1順位の相続人として扱われます。
母親は第2順位の相続人には含まれません。
ただし、胎児が死産となった場合、その胎児は相続人ではなかったとされます。
このため、胎児が死産となった場合には、相続人は母親だけとなります。
相続人に胎児がいる場合、胎児が生まれるまで「誰が相続人となるか」が確定しないため、通常、生まれてから遺産分割協議に加わるのが一般的です。
生まれたばかりの子供は判断能力がないため、誰かがその子供に代わって遺産分割協議に参加しなければなりません。
しかし、相続以外の場面では親が子供の代理人となりますが、相続に関しては妻と生まれたばかりの子供は法的に利害が対立するとみなされます。
例えば、妻が子供に代わって相続放棄を行った場合、妻がすべての遺産を相続することになります。
このため、遺産分割協議においては生まれたばかりの子供のために特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人は、親権者とその子の利害が対立する場合に、家庭裁判所が専任する代理人です。
特別代理人となるために特別な資格は必要ありませんが、候補者の情報を裁判所に提供し、裁判所が具体的な状況を考慮して適格性を判断します。
胎児がいる場合の相続は複雑な問題を含むため、法的なアドバイスを受けることが重要です。
特に相続における代理人の選任や手続きについては、専門家の指導を受けながら進めることをおすすめします。
適切な対応が行われることで、胎児も含めた相続プロセスが円滑に進行します。
非嫡出子の相続
非嫡出子(いわゆる隠し子)の存在が明らかになった場合、相続はさらに複雑になります。
まず、非嫡出子とは何かを理解することから始めましょう。
これは、法律上の夫婦でない相手との間に生まれた子供のことを指します。
一方、法律上夫婦と認められた相手との子供のことを嫡出子と呼びます。
次に、非嫡出子の相続権について考えてみましょう。
一般的に、非嫡出子は、他の法定相続人と同じく相続権を有します。
相続権は、民法により定められており、非嫡出子は第1順位の相続人となります。
しかし、実際の相続過程では、さまざまな要素が影響を及ぼすことがあります。
例えば、遺言が存在する場合や他の相続人との関係性などが考慮されます。
また、遺産分割や遺留分などの問題も発生する可能性があります。
離婚した相手との子の相続
相続は、私たちの生活に深く関わる重要なテーマです。
特に、離婚や再婚を経験した親の子供の相続は、法律的な規定や手続きが複雑であり、理解するのが難しい場合があります。
まず、親が離婚や再婚を経験していても、子供が相続人となる権利を失うことはありません。
これは、子供が実の親から生まれたものであれば、その親が亡くなった場合には相続人となる権利があるからです。
しかし、別れた夫や妻との間の子が、別の再婚相手との間で養子縁組をした場合は、話がやや複雑になります。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。
特別養子縁組をした場合には、あなたの実の親との相続のつながりが切れることになります。
配偶者と実子と養子の相続
養子の存在が明らかになった場合、相続はさらに複雑になります。
まず、養子とは何かを理解することから始めましょう。
これは、血縁関係がなくても法律上は親子関係が認められるため、実子と同じように相続人になる権利があることを指します。
ただし、養子縁組の届出をしないと、相続人になるための要件を満たしません。
次に、養子縁組の種類について考えてみましょう。
「一般的な養子縁組」と「特殊な養子縁組」の二つの形式が存在します。
特別養子縁組をした場合は、実親との相続関係が断ち切られることになります。
普通養子縁組の場合、子供は実親と養親の両方の相続権を持つため、実親が亡くなった場合でも養親の財産を相続できます。
また、養子が養子縁組後に子供をもうけた場合、その子供は代襲相続人として、養親の財産を相続できます。
行方不明者の相続
行方不明者の存在が明らかになった場合、相続はさらに複雑になります。
まず、行方不明者とは何かを理解することから始めましょう。
これは、相続が発生した時点で行方不明者がいる場合、その人と連絡を取るべくあらゆる手段を講じる必要があることを指します。
次に、行方不明者と連絡を取る方法について考えてみましょう。
戸籍からわかる本籍地や、これまでの居住地などを調べて、行方不明者の居場所を特定します。
行方不明者との連絡がどうしても取れない場合、現れるまで待ち続けることもできません。
そのため、不在者財産管理人または失踪宣告のいずれかの手段を講じることになります。
不在者財産管理人とは、その名前が示す通り、行方不明者の代理として、その人の財産を管理する役割を果たす人のことを指します。
遺産分割協議に参加するかどうかは、不在者財産管理人の判断となります。
「失踪宣告」は、家庭裁判所に申し立てを行い、行方不明となっている人を法律上死亡したものとみなしてもらう方法です。
法定相続人がいない
相続人が一人も存在しない人が遺産を遺して死亡した場合、その遺産は最終的に国庫に移されることになります。
まず、相続人がいない状態とは何かを理解することから始めましょう。
これは、単に親族がいない場合だけでなく、本来相続人となる人はいるけれど全員が相続放棄をしているような場合も含みます。
次に、相続人がいないと、その財産は民法上の法人という扱いになります。
つまり、その財産は相続人によって管理されるのではなく、相続財産管理人によって管理されることになります。
相続財産管理人は、相続人がいないかどうかを調査します。
一定の期間にわたる調査の後、相続人が特定できなかった場合、その財産は国庫に預けられることとなります。
血縁関係のない人でも、遺言を残すことにより相続人を選べます。
したがって、ここでの「相続人がいない」とは、「親族が存在せず、遺言も存在しない状況」を指します。
相続放棄
相続は、私たちの生活に深く関わる重要なテーマです。
まず、相続放棄とは何かを理解することから始めましょう。
相続財産には、プラスの財産(現預金や不動産などの資産)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い税金などの負債)も含まれることがあります。
マイナスの財産を相続した場合、その負債を返済する義務が発生します。負債の額によっては、人生を大きく左右する可能性があります。
相続放棄をすることで、マイナスの財産を相続せずに済みます。
そのため、自分の人生を自分で決めたい人にとっては、相続放棄は有効な選択肢となります。
次に、限定承認とは何かについてです。
限定承認とは、プラスの財産を相続し、マイナスの財産を相続しない方法です。
具体的には、相続財産の調査を行い、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続します。
限定承認をすることで、マイナスの財産を相続せずに、プラスの財産を相続できます。
しかし、限定承認は相続人となる人全員が共同で行う必要があります。
例えば、遺産の全体的な価値が不確定であるとき、借金の負担を避けつつ、家族が代々引き継いできた土地を保持したいという状況においても、限定承認は有益な選択となり得ます。
相続人廃除
「この人は相続人としない」と定められている人がいる場合、その人は相続人となる権利を失います。
相続人となる権利を失うことを相続人の廃除と呼びます。
まず、相続人の廃除とは何かを理解することから始めましょう。
相続人の廃除とは、厳密にいうと、遺言に相続人の廃除を記述するだけでは、相続人の廃除が認められません。
相続執行者は、遺言の内容に従って、家庭裁判所に相続人廃除の請求を行う必要があります。
家庭裁判所は、相続人の廃除について慎重に判断を行い、よほどのことがない限りは相続人の廃除を認めていません。
相続人の資格が剥奪されたとき、その情報は戸籍に記録され、相続人の資格が剥奪された人を除外して遺産の分割についての協議を進行することが可能となります。
相続欠格
民法891条に該当する不正行為を行った人は、法律上の相続人となる資格を失う可能性があります。
これは、相続権が剥奪されるという事態を意味します。
相続人となる権利を剥奪されることを相続欠格といいます。
まず、相続欠格とは何かを理解することから始めましょう。
相続の資格がないとされるのは、死亡した人を殺害した相続人、死亡した人の殺害を告発しなかった相続人、または詐欺や強制により遺言に影響を及ぼした相続人です。
上記の相続人は、相続欠格にあたります。
次に、相続欠格が認められる条件について考えてみましょう。
家庭裁判所は相続欠格についてかなり慎重に判断を行っており、よほどのことがない限りは相続欠格は認めていません。
しかし、相続資格が剥奪された場合、その情報は戸籍に記録され、その人を除外して遺産の分割についての協議を進行することが可能となります。
法定相続人を確認する方法
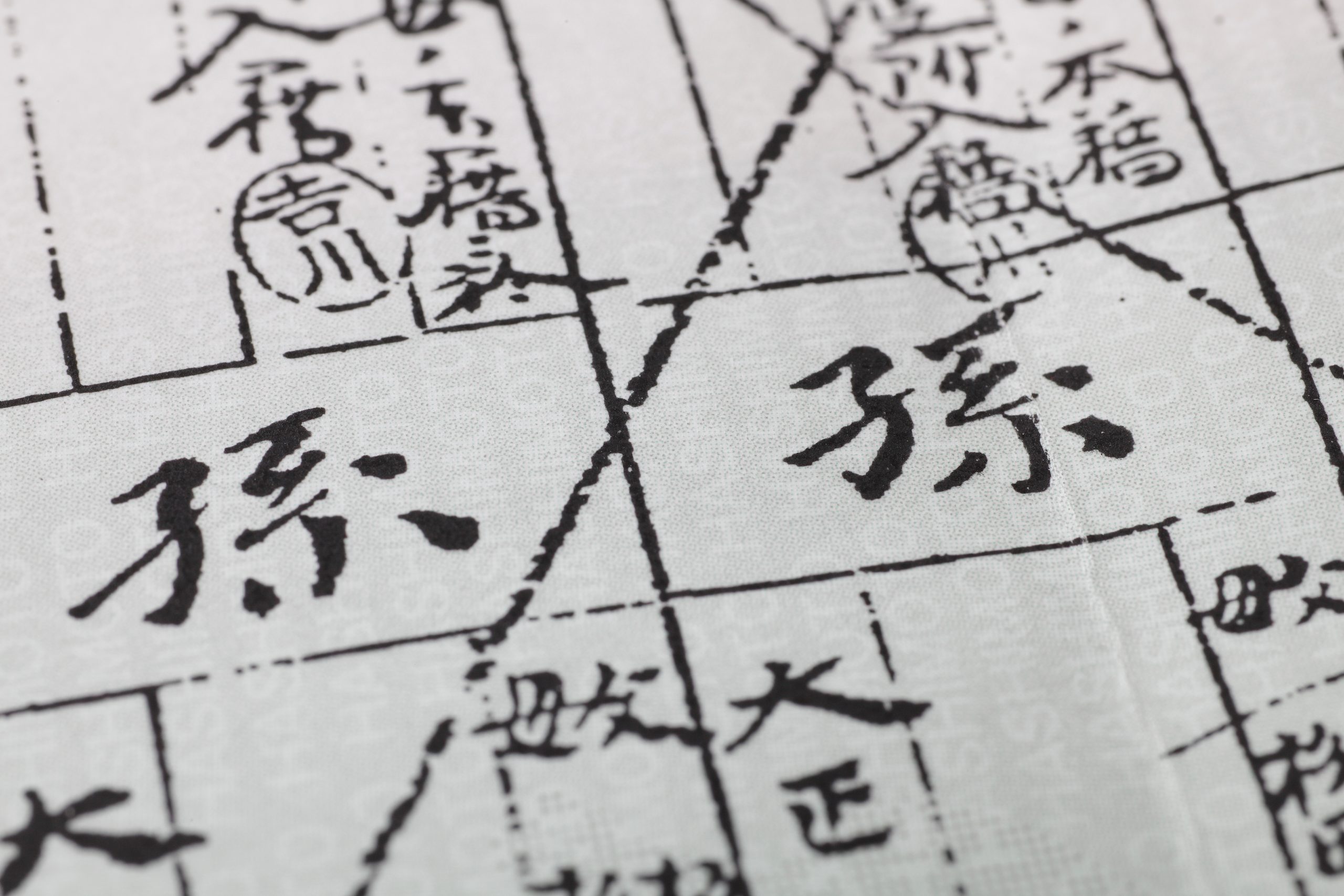
亡くなった方の相続人が誰であるのかを確認する方法は、戸籍謄本をたどることです。
まず、戸籍謄本とは何かを理解することから始めましょう。
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている内容を証明する公文書です。
相続手続きや各種手続きに必要な書類として利用されます。
また、代理人に申請を委任することも可能です。
委任する場合は、委任状と代理人の本人確認書類、印鑑を用意する必要があります。
戸籍謄本は転籍や婚姻などを理由に、新しい戸籍謄本が作られます。
漏れることなく確認していくためには、亡くなった方の出生から亡くなった方までの連続した戸籍謄本を取得する必要があります。
取得した戸籍謄本の確認ポイントは以下の通りです。
- 戸籍謄本の改製日、編製日、死亡日、入籍日、除籍日から証明機関を確認
- 異動した経緯を従前戸籍から確認
戸籍謄本の請求に必要な書類は以下の通りです。
- 請求用紙
- 請求者の戸籍謄本
- 請求者の本人確認書類
- 委任状(第三者に委任する場合)
- 返信用封筒(郵送で請求する場合)
- 定額小為替(郵送で請求する場合)
関連記事法定相続人とは、故人の財産を相続する権利を法律で定められた人々のことを指します。 相続人には配偶者や子供、親などが含まれ、それぞれの立場や関係性によって相続の順位や割合が違います。 この記事では、以下のポイントを中心に解説します。 […]
遺言書の効力

相続は、私たちの生活に深く関わる重要な要素の一つです。
法定相続人とは、民法で定められた順位に従って、相続権を有する者のことをいいます。
また、法定相続分とは、法定相続人が相続財産を相続する割合のことをいいます。
しかし、必ずしも法定相続分で財産を分ける必要はありません。
被相続人が遺言を作成して、遺産分割の指定をした場合、その指定に従って財産を分けられます。
亡くなった方が遺言書を残していれば、法定相続分よりも遺言書が優先されます。
まず、遺言書とは何かを理解することから始めましょう。
遺言書とは、亡くなった方が自身の財産をどのように分けるかを記した文書のことを指します。
遺言書が存在する場合、その内容が法定相続分よりも優先されます。
次に、遺留分についてです。
「遺留分」とは、相続人が最低限相続できる財産の割合を指します。
遺留分を無視して財産を継承した場合、遺留分を多く受け取った相続人に対して遺留分の請求が可能です。
遺言書は、人生の最終章において個人が残すことのできる最も強力な法的文書の一つです。 これは、私たちがこの世を去った後に財産や大切な思い出がどのように扱われるかを定めるものであり、愛する方々への最後のメッセージとも言えます。 相続において[…]
遺留分対象の相続財産

遺留分とは、配偶者・直系卑属・直系尊属などの相続人が、遺言によっても奪うことができない最低限の遺産取得割合のことをいいます。
この遺留分は、相続人の生活保障を目的として設けられた制度です。
遺言によって相続分が減らされた場合でも、遺留分を請求することで、最低限の遺産を受け取れます。
遺言は法定相続分より優先されますが、遺留分は遺言に優先するとされています。
まず、遺留分とは何かを理解することから始めましょう。
遺留分は、配偶者や直系卑属が相続人となる場合は「基礎財産×法定相続分×2分の1」、直系尊属だけが相続人となる場合、相続税の計算は「基本的な財産額×法定相続分×1/3」によって行われます。
次に、遺留分の対象財産についてです。
遺留分の対象となる財産は、遺贈された財産、被相続人が亡くなる1年以内に譲渡された財産、遺留分の侵害を知って行われた贈与、特別受益に該当する財産などです。
これらの財産を合計したものが、相続開始の時において被相続人が有した財産であり、遺留分の対象となります。
本記事では、相続遺留分について以下の点を中心にご紹介します! 遺留分とは 遺留分を主張する権利を持つ相続人 遺留分侵害額請求の時効 相続遺留分について理解するためにもご参考いただけると幸いです。 ぜひ最後までお[…]
遺留分財産を計算する方法

遺留分の計算方法とは何かを理解することから始めましょう。
遺留分算定基礎財産とは、遺留分の対象となる財産の総額を算定するための財産のことです。
遺留分算定基礎財産は、相続開始時の積極財産(現金や不動産など)に、生前贈与された財産を加えた金額から、相続開始時に負っていた消極財産(借入金や買掛金など)を差し引いて算定します。
具体的な計算式は、以下のとおりです。
遺留分算定基礎財産=相続開始時の積極財産+贈与した財産-相続開始時に負っていた消極財産
遺留分算定基礎財産は、遺留分の請求を行う際に重要となる財産です。
遺留分を請求する可能性がある方は、遺留分算定基礎財産を正しく把握しておきましょう。
相続人が妻、長男、次男で、積極財産が銀行預金4,000万円、消極財産がローン200万円、相続開始の1年以内に、長男に600万円贈与した場合を計算します。
4,000万円(預金額)+500万円(贈与額)ー200万円(負債額)=4,300万円(遺留分算定起訴財産)
遺留分の割合は「基礎財産×法定相続分×2分の1」となり、以下のようになります。
妻の遺留分:4,300万円×1/2×1/2=1,075万円
長男の遺留分:(4,300万円×1/2×1/2×1/2)ー600万円=▲62万円
次男の遺留分:4,300万円×1/2×1/2×1/2=537万円
長男は遺留分額がマイナスとなるため、遺留分侵害額請求はできません。
相続登記の義務化

所有者不明土地が全国で増え、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
問題解決のため、これまで任意だった相続登記が、2024年4月から義務化されます。
相続登記とは、不動産(土地・建物)を相続で取得した相続人が、名義を変更する手続きです。
相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、不動産の売却や担保設定などの際に、手続きが複雑になる可能性があります。
相続登記を忘れずに、早めに済ませましょう。
相続順位の図に関するよくある質問

遺産分割協議で相続順位を変えることはできるか?
相続順位は民法に基づいて定められており、遺産分割協議で変更することはできません。遺産分割協議にはすべての法定相続人が参加する必要があり、一部の相続人を無視することはできません。
ただし、遺産分割協議では各相続人の相続割合を変更することは可能です。全ての法定相続人の同意があれば、法定相続分とは異なる割合で相続することができます。
遺言があると相続順位は変わるか?
遺言がある場合、相続の順番自体は変わりませんが、法定相続よりも遺言が優先されます。つまり、遺言によって特定の相続人に法定相続分を超える財産を譲ることが可能です。これにより、被相続人が希望する相続分を実現することができます。
ただし、遺言を作成する際には「遺留分」に注意が必要です。遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる財産の割合を指します。遺言でこの遺留分を侵害することはできません。もし遺言によって遺留分が侵害された場合、侵害を受けた相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
そのため、遺言を作成する際は、他の法定相続人の遺留分を侵害しないよう十分に配慮することが重要です。
離婚した元妻・元夫の相続順位とは?
離婚すると、法律上の家族関係が解消されるため、元妻や元夫は相続人としての権利を持ちません。したがって、相続順位も与えられません。
しかし、離婚した後も子どもとの親子関係は続くため、子どもは親の相続権を持ち、相続順位は第1位となります。
相続放棄をすると順位がどうなるの?
相続放棄をした場合、その人は初めから相続人でなかったとみなされます。その結果、次順位の相続人に相続権が移ります。例えば、相続放棄した子がいる場合、孫や兄弟姉妹に相続権が移行することがあります。
全員が相続放棄した場合は
法定相続人全員が相続放棄をすると、相続財産は最終的に家庭裁判所の手続きを経て国庫に帰属します。
次順位の相続人とは誰になるか
民法では相続順位が定められており、被相続人の子が最優先、第2順位が直系尊属(親や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹です。上位の相続人がいない場合や放棄した場合に、次順位の相続人が相続権を持つことになります。
兄弟の相続順位とは?
被相続人に子ども(またはその代襲相続人)や直系尊属(親や祖父母)がいない場合、兄弟姉妹が相続順位第3位として相続権を持ちます。
兄弟姉妹が亡くなっている場合、誰が相続するのか
亡くなった兄弟姉妹に子ども(甥や姪)がいれば、甥や姪が代襲相続します。甥や姪がいない場合、残りの兄弟姉妹が相続します。
遺言がある場合、兄弟姉妹の相続権はどうなるのか
遺言が優先されるため、遺言書の内容次第で兄弟姉妹が財産を相続しないこともあります。なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
相続順位の図まとめ

ここまで相続順位の図についてお伝えしてきました。
法定順位の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続順位とは法定相続人内の順位のことである
- 離婚相手との子の相続権は、婚姻中の相手との子と同等にある
- 法定相続人がいない場合、遺言書があればその内容通り、遺言書がなければ国家の財産になる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。





