相続は、人生における大きな出来事の一つです。
大切な家族を亡くした後、残された財産をどのように処理するか、という問題に直面することになります。
相続税は、その際に避けて通れない問題です。
しかし、「相続税がいくらになるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、相続税額の計算方法や、相続税がいくらかかるのかを把握する具体的な方法についてご説明します。
- 相続税とは
- 相続税がいくらかかるのかを知る方法とは
- 相続税の申告は判断方法とは
相続税はいくらかかるかについてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続税とは

相続税とは、亡くなった人の遺産を相続した人に課税される税金のことです。
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を引いた額に対して課税されます。
基礎控除額は、300万円+(600万円×法定相続人の数)です。
相続税の税率は、5%から45%まで累進課税方式で課税されます。
相続税は、相続開始後10ヶ月以内に申告・納付する必要があります。
相続税対策としては、生前贈与や生命保険を活用することが有効です。
詳しくは、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続税は、多くの方にとって複雑で気になる要素の一つではないでしょうか。 特に、「相続税はいくらからかかるのか」という疑問は、相続に直面した際に非常に重要です。 この記事では、相続税はいくらからかについて以下の点を中心にご紹介します![…]
相続税の対象になる財産は?

ご両親などから財産を相続した際、相続税がかかることをご存知ですか?
相続税は、亡くなった方の財産を相続した際に発生する税金です。
しかし、「相続税の対象になる財産は、具体的にどのようなものがあるのか?」と疑問に思われる方も多いでしょう。
この記事では、相続税の対象となる財産の範囲について解説します。
本来の相続財産
相続税の対象となる財産には、主に「本来の相続財産」として、故人が生前に所有していた財産が含まれます。
具体的には、土地や建物、現金、預貯金、有価証券、さらには故人の持つ借金や債務などが該当します。
これらは、プラスの財産もマイナスの財産も含め、全体が課税対象の基礎になります。
また、生命保険の死亡保険金や死亡退職金も、一定条件のもとで相続財産として見なされるため、相続税申告においては把握が必要です。
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産
相続税の対象には、相続時精算課税制度を利用した生前贈与も含まれます。
通常、贈与税は年間110万円までが非課税ですが、この制度を利用すると、特定の親族へ累計2,500万円まで非課税で贈与可能です。
ただし、贈与者が亡くなった際には、それまでに贈与した財産が相続財産とみなされ、相続税の課税対象に加算されます。
そのため、相続時精算課税を適用した場合、贈与財産も含めた資産全体で税額を計算する必要があります。
生前に贈与された財産(相続開始前7年以内)
相続税の課税対象には、被相続人が亡くなる前7年以内に行われた贈与財産も含まれます。
特に、死亡直前3年以内の贈与財産は全額が相続財産に加算され、相続税の計算基礎に組み入れられるため注意が必要です。
3年以上7年以内の贈与については、累計の贈与額が基礎控除を超える部分が課税対象に加算されるルールが設けられています。
この制度は、財産を生前贈与で減少させて相続税を軽減する対策の抑制を目的としています。
相続税の基礎控除額は

相続税の基礎控除額は、遺産の額が一定金額を超えた場合に適用される控除で、相続税がかかるかどうかの判断に重要な役割を持ちます。
2024年現在、基礎控除額の計算は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で行われます。このため、例えば法定相続人が2人いる場合、基礎控除額は4,200万円になります。
この金額以下の遺産には相続税はかからないため、相続の負担を軽減するために、相続人数や基礎控除額の確認が重要です。
相続税の基礎控除は、相続財産から一定額を控除し、その結果課税される額を決定するための重要な要素です。 この控除により、多くのケースで相続税の負担が軽減されるため、その計算方法と適用条件を理解することが非常に重要です。 この記事では、[…]
相続税額の計算方法

相続財産の評価額を調べ、遺産総額を算出する
相続税の計算は、まず相続財産の評価額を調べて遺産総額を算出することが最初です。相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産のことを言います。
これには不動産、預貯金、株式などが含まれます。
これらの財産は、それぞれの評価基準に沿って評価されます。
不動産の評価は、公示価格や路線価を基準に行われ、預貯金や株式はその時の市場価格で評価されます。
また、評価額は被相続人が亡くなった時の価格を基準にします。
このようにして算出されたそれぞれの財産の評価額を合計することで、遺産総額が算出されます。
遺産総額から基礎控除額を引く
次に、遺産総額から基礎控除額を引くことについて説明します。
基礎控除額は
- 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
で計算されます。
この結果、課税される遺産の総額(課税遺産総額)が算出されます。
基礎控除額とは、相続税が課される財産の最低限の額を定めたものであり、小規模な相続における税負担を軽減することを目的としています。
また、基礎控除額は法定相続人の数に応じて増加するため、相続人が多い方が相続税の負担は軽減されます。
法定相続分で金額を割り振る
課税遺産総額を、各法定相続人が民法で定められた法定相続分に従って取得したと仮定し、それぞれの法定相続分に基づく取得額を算出します。
法定相続分とは、相続人が取得する相続財産について、民法で規定された相続割合を指します。
例えば、配偶者と子供1人の場合配偶者の法定相続分は1/2、子供の法定相続分は1/2です。
このようにして求められた各相続人の取得額に基づき、次のステップである税額の算定が行われます。
上記の金額に相続税の税率をかけ、相続税の総額を算出する
各法定相続人の法定相続分に応じた取得額に税率を適用し、相続税の総額の基準となる税額を計算します。
この速算表に当てはめて算出した税額を合計したものが、相続税の総額になります。
相続税の税率は超過累進課税方式が採用されており、取得額が大きくなるほど高い税率が適用されます。
これにより、大規模な相続に対する税金の負担が増加します。
実際に相続した割合に応じ納付税額を算出する
最後に、相続税の総額を、各相続人が実際に相続した割合に応じて按分し、それぞれの納付額を計算します。
これにより、各相続人が納付するべき相続税額が明確になります。
この計算は、各相続人が実際に受け取った遺産の割合を基に行われます。
したがって、実際に受け取った遺産の割合が大きいほど、納付すべき相続税額も大きくなります。
以上が相続税の計算手順です。
一見複雑に思えるかもしれませんが、順を追って進めれば理解できる内容です。
相続税の計算は、正確な知識と理解があれば適切に行うことができます。
必要な情報を揃え、適切な手順で進めることで、適切な相続税額を計算することができます。
これらの知識を持つことで、相続税について深く知ることができるでしょう。
相続税の計算は、初めての方にとっては難しく感じるかもしれません。 しかし、具体的な計算例を通じて、そのプロセスを理解することが可能です。 本記事では、相続税の計算例について以下の点を中心にご紹介します。 相続税の税率の仕組[…]
3,600万円超でも相続税がかからないパターン

相続税の基礎控除額は一般的に3,600万円とされていますが、実は、相続財産が3,600万円を超えていても相続税がかからないケースがあります。
相続税の計算は複雑で、様々な要因によって税額が変動するため、「相続財産が3,600万円を超えたから必ず相続税がかかる」とは限りません。
この記事では、3,600万円を超えていても相続税がかからないパターンを解説します。
基礎控除額を超えない場合
相続税は「基礎控除額」を超えない限り発生しないため、遺産額が基礎控除内に収まれば課税されません。
2024年現在の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められており、例えば法定相続人が1人の場合であれば3,600万円が基礎控除額になります。
そのため、遺産額が3,600万円以下であれば、相続税の申告は不要です。これにより、比較的小規模な遺産を持つ家庭では、相続税がかからないケースが多くなります。
また、控除額が適用されることで、法定相続人の数が増えるとより高額の遺産でも非課税となる可能性が高まります。
基礎控除額を超える場合
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えても、特定の非課税制度を利用することで相続税を抑えることができます。
例えば、「小規模宅地等の特例」では、被相続人が住んでいた土地の一定面積までが大幅に減額され、さらに「死亡保険金の非課税枠」や「死亡退職金の非課税枠」を活用することで、実際の相続税の対象額を減らすことが可能です。
これらの制度を上手く使うことで、控除額を超えていても相続税がかからないケースがあります。
配偶者に対する相続税額の軽減
「配偶者に対する相続税額の軽減」は、相続税の負担を大幅に減らすことができる特例制度で、配偶者が相続する財産に対して一定額まで相続税がかからないようにするものです。
この制度を利用することで、配偶者が取得した相続財産のうち、法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い方までが非課税となります。
そのため、配偶者は生涯を通じて安心して生活するための資産を保持しやすくなります。
この軽減措置を利用するには、相続税申告時に適切な手続きを行うことが求められます。
未成年者控除
「未成年者控除」は、被相続人から財産を相続した未成年者に対する相続税の負担を軽減するための制度です。
具体的には、相続人が20歳未満である場合、その年齢に応じて控除額が設定されます。
控除額は「20歳までの年数 × 10万円」となり、未成年者が成人に達するまでの年数分を計算し控除できます。
たとえば、10歳の子が相続する場合、10年分として100万円が控除される計算です。
未成年者が安心して将来を築けるよう配慮された制度で、親族などが後見人として申請手続きを行うことも可能です。
障害者控除
「障害者控除」は、相続人が障害者である場合に相続税の負担を軽減するための制度です。控除額は「85歳までの年数 × 10万円」とされ、特別障害者であれば1年につき20万円となります。
この控除は、相続人の生活支援を目的とし、障害のある相続人が経済的な負担を減らして安心して生活できるよう考慮されています。
また、この控除額は他の控除と併用できるため、税額の負担軽減効果が大きくなります。
相次相続控除
相次相続控除は、相続税の軽減措置で、2回以上相続が発生した場合に適用されます。
例えば、親から子への相続後、すぐに子から孫への相続があった場合、前回の相続税額の一部を次回の相続税から控除できます。
これにより、相続税の負担が軽くなり、相続人にとっては負担を軽減できるメリットがあります。
相続税の納税義務が重なることを避けるために有効な制度です。
外国の財産に対する相続税額の控除
外国の財産に対する相続税額の控除は、外国にある財産に対して相続税が課税された場合に、その相続税額の一部を日本で支払う相続税から控除できる制度です。
これにより、二重課税を防ぎ、相続人の負担を軽減することができます。
ただし、控除を受けるためには一定の条件があり、相続財産が海外にあることや、外国での相続税の納付証明などが求められることがあります。
贈与税額控除(暦年課税・相続時精算課税)
贈与税額控除は、贈与者から受けた贈与財産に対する税額を軽減する制度です。
主に2つの課税方法があります。一つは暦年課税で、年間110万円までの贈与が非課税となります。
もう一つは相続時精算課税で、贈与税は一度に課税されますが相続時にその分が相続財産に加算され、相続税を支払う際に精算します。
いずれの方法も適用には一定の条件があります。
相続税の算出に必要な情報とは

相続が発生した際、多くの方が「相続税」の計算に頭を悩ませることでしょう。
相続税の計算は、様々な要素が複雑に絡み合い、専門家でも正確に算出するのは容易ではありません。
では、相続税の計算には、一体どのような情報が必要なのでしょうか?
この記事では、相続税の算出に必要な情報について解説します。
遺産の対象を正しく把握する
相続税を算出するためには、遺産の対象を正しく把握することが重要です。
遺産には現金や不動産、株式などが含まれ、被相続人が所有していた財産はすべて評価対象となります。
遺産には借金や未払金も含まれ、これらは差し引かれるため、正確に整理し、全ての資産と負債を洗い出すことが必要です。
また、生前に行われた贈与も含まれる場合があるため、その情報も確認することが求められます。
法定相続人の数
相続税を算出する際に重要な要素の一つは法定相続人の数です。
法定相続人とは、法律に基づいて相続権を有する人物で、配偶者や子ども、親などが含まれます。
相続人の数によって、相続税の基礎控除額が決まり、その後の相続税額が変動します。
相続人が多い場合、控除額が増えるため、税負担が軽減されることになります。
適切に相続人を確認することは、正確な相続税の計算に不可欠です。
相続税がいくらかかるのかを知る方法とは
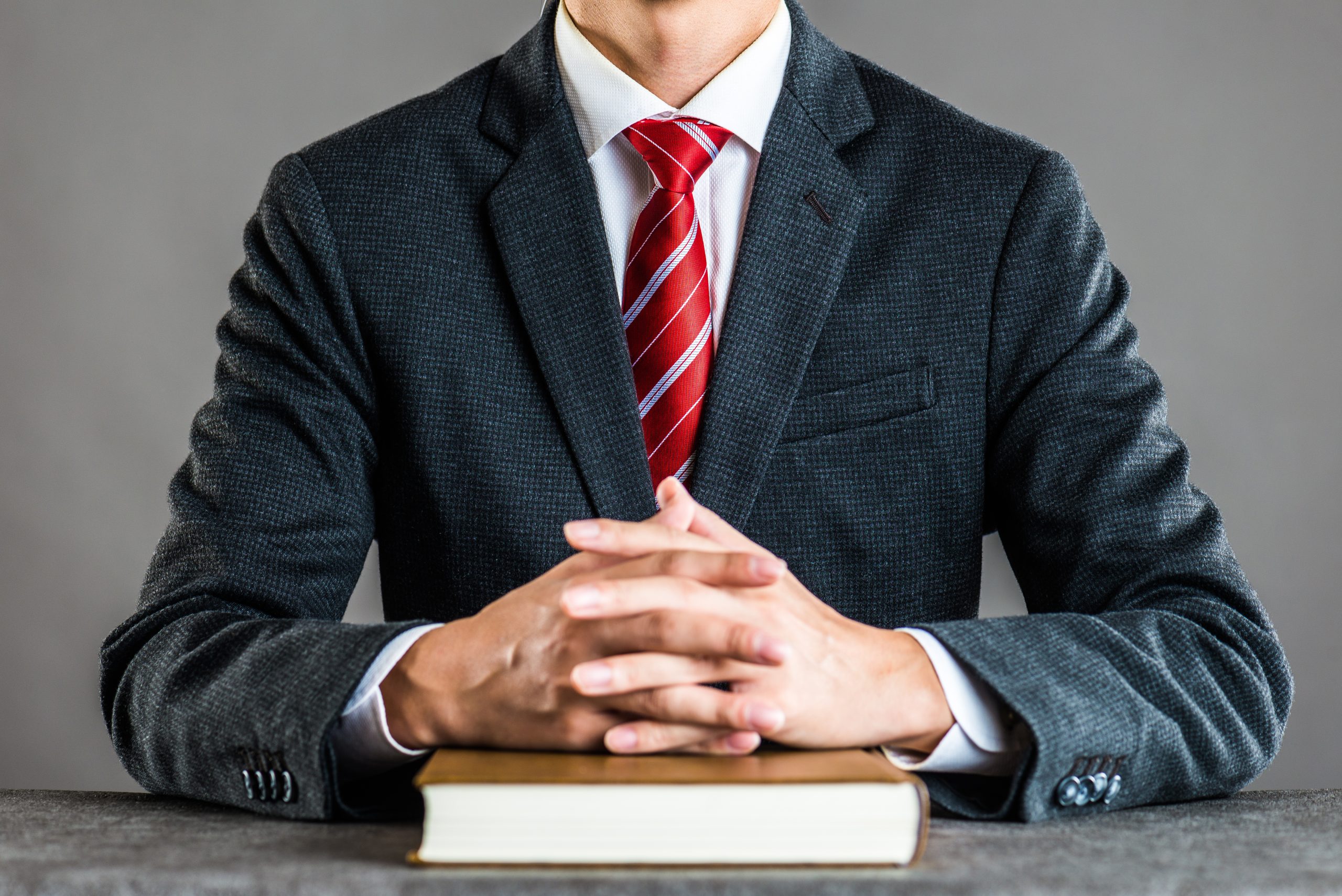
相続税は、亡くなった方の財産を相続した際に発生する税金です。
しかし、相続税の計算は複雑で、個々のケースによって大きく異なるため、正確な税額を把握するのは容易ではありません。
この記事では、相続税がいくらかかるか知る方法を解説します。
相続税の速算表で計算する
相続税の額を計算する方法の一つに、相続税の速算表を使用する方法があります。
速算表は、相続財産の総額と法定相続人の数を基に、相続税額を簡便に計算できるツールです。
この表に従い、課税価格をもとに計算を行うことで、相続税の目安を得ることができます。ただし、速算表はあくまで目安であり、詳細な計算には専門的な知識が必要です。
相続税の早見表を見る
相続税がいくらかかるかを知る方法の一つとして「相続税の早見表」を活用することができます。
早見表は、遺産総額と法定相続人の数をもとに、相続税額を簡単に把握できるツールです。この表は、一般的な相続税の目安を計算するために便利で、相続人が誰か、財産の種類や評価額に関する詳細な計算を省略できます。
早見表の使い方は非常にシンプルで、まず遺産総額(プラスの財産とマイナスの財産を含む)を把握します。
次に、相続人の人数に応じて表の該当する部分を見つけ、予想される相続税額をチェックします。
この段階で、税額を一目で確認できるため、相続税の負担感が軽減されるでしょう。
ただし、早見表で示される税額はあくまで概算であり、実際の相続税額を確定するには詳細な計算が必要です。
特に、特例の適用や相続財産の評価方法に影響を受けるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします
シミュレーションソフトを使う
相続税の額を知る方法として、シミュレーションソフトの利用は非常に便利です。
これらのソフトウェアは、遺産総額や相続人の人数、相続財産の内容を入力することで、予想される相続税額を自動で計算してくれます。
特に、財産の評価額や特例の適用など複雑な計算を迅速に行えるため、相続人が相続税額の目安を早期に把握するために役立ちます。
シミュレーションソフトを使用することで、相続税額の概算ができるだけでなく、いくつかのシナリオを試すことも可能です。
例えば、相続する財産を異なる方法で分割する場合や、贈与税などの関連税務も考慮に入れたシミュレーションができます。
これにより、最適な相続プランを立てる手助けとなり、相続税負担の軽減策を検討することも可能になります。
また、多くのシミュレーションソフトは無料で提供されているため、手軽に試してみることができます。
相続税の申告は期限内に

相続税の申告は、相続が発生した日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
この期間を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があり、税負担が増加します。したがって、期限内に正確な申告を行うことが非常に重要です。
相続税の申告が必要かどうかは、遺産額や相続人の状況によって異なります。
例えば、遺産が基礎控除額を超えている場合や、特例の適用を受ける場合は申告が求められます。
申告期限を守るためには、相続財産の評価や相続人の確認、必要な書類の準備を早めに進めることが求められます。
もし申告が間に合わない場合には、申告期限後に手続きを行う「期限後申告」を利用することも可能ですが、この場合は加算税が課されるため注意が必要です。
最善の方法は、期限内に適切に申告を行うことです。
相続税の申告の判断方法とは

相続税は、亡くなった方の財産を相続した際に発生する税金です。
しかし、全ての相続で申告が必要となるわけではありません。
この記事では、相続税の申告が必要かどうかを判断する方法を解説します。
法定相続人1人なら基礎控除3,600万円以下は申告不要
相続税の申告が必要かどうかは、基礎控除額を超えたかどうかで判断されます。
法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円です。これを超える遺産を相続した場合は、相続税の申告が必要になります。
逆に、遺産総額が3,600万円以下であれば、申告の必要はありません。
例えば、相続財産が3,000万円だった場合、基礎控除額の3,600万円に収まっているため、相続税の申告は不要です。
しかし、相続財産が4,000万円の場合、基礎控除を超えた400万円分に相続税が課税され、申告が必要になります。
この基準は法定相続人が1人の場合に適用されます。
相続人が2人以上であれば、基礎控除額が増えますので、控除額を確認することが重要です。
相続税の申告は遺産の評価や法定相続人の数に基づいて判断されるため、事前にしっかりとした確認が求められます。
相続税が発生したら申告が必要
相続税の申告が必要かどうかは、基礎控除額を超えたかどうかで判断されます。
法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円です。
これを超える遺産を相続した場合は、相続税の申告が必要になります。逆に、遺産総額が3,600万円以下であれば、申告の必要はありません。
例えば、相続財産が3,000万円だった場合、基礎控除額の3,600万円に収まっているため、相続税の申告は不要です。
しかし、相続財産が4,000万円の場合、基礎控除を超えた400万円分に相続税が課税され、申告が必要になります。
この基準は法定相続人が1人の場合に適用されます。
相続人が2人以上であれば、基礎控除額が増えますので、控除額を確認することが重要です。
相続税の申告は遺産の評価や法定相続人の数に基づいて判断されるため、事前にしっかりとした確認が求められます。
特例や控除を利用して無税になった場合
相続税の申告が必要かどうかを判断する際、特例や控除を活用することで、最終的に相続税が無税となる場合があります。
たとえば、配偶者控除や未成年者控除、障害者控除などの特例を利用すると、相続税の負担を大幅に軽減できることがあります。
特に、配偶者控除は、配偶者が相続する財産に対して高額の控除が適用されるため、配偶者が相続人であれば、相続税が無税になる場合が多いです。
また、相続時精算課税制度を利用すると、一定の条件下で贈与税と相続税をまとめて計算し、相続税が軽減される可能性があります。
さらに、相次相続控除や財産評価の見直しなども考慮に入れることで、相続税を減らすことができます。
これらの特例や控除をうまく活用することで、相続税の申告をする必要がなくなり、無税となることがあります。
ただし、控除や特例の適用を受けるためには、正確な申告が求められるため、税理士などの専門家に相談して、申告を行うことが重要です。
相続税はいくらかかるかについてまとめ

相続税はいくらかかるかについてお伝えしてきました。
相続税はいくらかかるかについてまとめると以下の通りです。
- 相続税とは、亡くなった人の遺産を相続した人に課税される税金のことで、 相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を引いた額に対して課税される
- 相続税の額を計算する方法は、相続税の速算表を使用する方法や早見表は、遺産総額と法定相続人の数をもとに、相続税額を簡単に把握できるツールを使う方法がある
- 相続税の申告が必要かどうかは、基礎控除額を超えたかどうかで判断され、法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円で、これを超える遺産を相続した場合は、相続税の申告が必要である
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




