相続税とは、亡くなった方の財産を相続するときにかかる税金です。
相続税は、相続財産の評価額や相続人の数などによって計算されますが、その計算に誤りがあった場合、相続税を過払いしてしまうことがあります。
過払いした相続税は、一定の手続きをすることで税務署から返金してもらうことができます。
この還付を受ける制度を「相続税還付制度」といいます。
この記事では、相続税の還付制度について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続税の還付制度
- 相続税還付制度の手続き
- 相続税還付制度のメリット
相続税の還付制度について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続税の還付

相続税還付は、過去に納付した相続税が実際の税負担額を上回っていた場合に、その超過分を国から返還してもらえる制度を指します。
この手続きは、相続税申告後に財産評価や計算ミスなどの誤りが発見された際に、特に重要となります。
相続税還付の概要
相続税還付制度を利用することで、相続人は過剰に支払った税金を取り戻すことが可能です。
相続税の還付手続きは、「更正の請求」という手続きを通じて行われ、税務署に対して過去の申告内容の見直しを求めることになります。
還付の適用を受けるためには、相続税の申告内容に誤りがあったことを証明し、正しい税額を算出する必要があります。
相続税還付の適用条件
相続税還付の適用を受けるためには、以下のような条件が満たされる必要があります。
- 財産評価の誤り:土地や不動産などの相続財産の評価額が、当初の申告時よりも低くなることが後に判明した場合。
特に土地の評価は、その位置や形状、利用可能性などによって大きく変動するため、再評価により税額が下方修正されることがあります。 - 計算ミス:相続税の計算過程でのミスが発見された場合。
これには、控除の適用漏れや、誤った税率の適用などが含まれます。 - 申告内容の見直し:相続財産に関する新たな情報が得られたり、法的な見解が変わったりして、当初の申告内容が不適切であったことが明らかになった場合。
これらの条件のいずれかが該当する場合、相続税の還付請求が可能となりますが、正確な評価や計算を行うためには専門的な知識が必要となるため、税理士や相続専門家に相談することが推奨されます。
また、還付請求には期限が設けられており、相続の開始を知った日の翌日から5年10ヶ月以内に請求を行う必要があるため、早めの行動が求められます。
相続税については、こちらの記事もお読みください。
相続税は、多くの方にとって複雑で気になる要素の一つではないでしょうか。 特に、「相続税はいくらからかかるのか」という疑問は、相続に直面した際に非常に重要です。 この記事では、相続税はいくらからかについて以下の点を中心にご紹介します![…]
還付期限と平均還付額

相続税還付に関する「還付期限」と「平均還付額」は、相続税申告後に過剰に納付した税金を取り戻す際の重要な要素です。
これらの要点を踏まえた上で、相続税還付の手続きを検討する際の参考情報を提供します。
還付期限について
相続税の還付請求には、明確な期限が設定されています。
具体的には、相続が発生し、その事実を知った翌日から数えて5年10ヶ月以内に還付請求を行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、たとえ過剰に税金を納付していたとしても、還付を受けることはできません。
したがって、相続税を納付した後は、速やかに申告内容を見直し、必要に応じて還付請求の手続きを進めることが重要です。
平均還付額について
相続税還付の平均額は、ケースによって大きく異なりますが、過去のデータによると、相続税還付を受けた場合の平均還付額は数百万円に上ることがあります。
具体的な額は、過剰に納付した税金の額や相続財産の評価額の見直しの結果によって変動します。
還付を受けるためには、相続財産の評価額の見直しや計算ミスの訂正など、具体的な根拠をもって税務署に更正の請求を行う必要があります。
相続税還付の手続きは複雑であり、専門的な知識を要するため、税理士や相続専門家に相談することが望ましいです。
還付請求の期限内に適切な手続きを行い、過剰に納付した税金を取り戻すことで、相続人の負担を軽減することが可能になります。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続税を過払いしてしまう理由

相続税を過払いしてしまう主な理由は、相続税申告過程における複雑な評価と計算の難しさにあります。
多くの場合、相続人や税理士が直面する評価の複雑さや、計算上の誤りが過払いの原因となっています。
相続財産の評価の難しさ
相続税の申告において、不動産や土地などの財産評価は非常に複雑です。
市場価値の変動、特定の財産の特性、利用可能性など、多くの要因が評価に影響を及ぼします。
特に土地の評価では、その位置、形状、周辺環境などが税額に大きく影響するため、正確な評価を行うことが難しく、結果として過剰な税額を申告してしまうことがあります。
計算ミス
相続税の計算は、多数の控除項目や税率の適用など、複雑なルールに基づいて行われます。
これらの計算過程でのミスや誤解が過払いの一因となり得ます。
例えば、適用可能な控除を見落としたり、誤った税率を適用したりすることで、実際よりも高い税額を算出してしまうことがあります。
専門知識の不足
相続税申告を担当する税理士の中には、相続税専門ではないため、相続税に関する特有の規定や評価方法に不慣れな場合があります。
この専門知識の不足が、不適切な財産評価や計算ミスに繋がり、結果的に相続税の過払いにつながることがあります。
これらの理由から、相続税を過払いしてしまうケースが発生します。
相続税の申告後にも、申告内容の見直しや専門家による評価の再検討を行うことで、過払い分の還付を受けることが可能です。
相続税の過払いを防ぐためには、申告前に専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続税還付手続きの流れ
相続税は、相続した財産の価値に応じて納める税金です。
しかし、相続した財産の価値は、必ずしも正確に分かるとは限りません。
特に、土地や株式などの価値は、市場の変動や評価方法によって大きく異なることがあります。
そのため、相続税の申告時に、財産の価値を高く見積もってしまい、相続税を多く支払ってしまうことがあります。
このような場合、相続税を納め過ぎた分を税務署から返してもらうことができます。
これを相続税還付と呼びます。
相続税還付を受けるには、相続税の更正の請求という手続きを行う必要があります。
ここでは、相続税還付の手続きの流れについて解説します。
更正の請求書を作成する
更正の請求書は、相続税の申告書と同じフォーマットで、相続財産の価値や相続税の計算方法などを記入します。
ただし、更正の請求をする理由や経緯、還付金の振込先なども記入する必要があります。
また、更正の請求の根拠となる証拠書類も添付します。
例えば、土地の価値を見直した場合は、測量図や写真などを添付します。
更正の請求書を税務署に提出する
更正の請求書を作成したら、管轄の税務署に提出します。
税務署は、提出された更正の請求書を審査し、請求内容を認めるかどうかを判断します。
審査には、数ヶ月から1年以上かかることもあります。
更正通知書を受け取る
税務署が更正の請求を認めた場合、更正通知書が送付されます。
更正通知書には、更正後の相続税額や還付金額などが記載されています。
更正通知書を受け取ったら、内容を確認し、異議がなければ、還付金の振込を待ちます。
還付金を受け取る
税務署は、更正通知書を送付した後、1〜2ヶ月程度で、指定した口座に還付金を振り込みます。
還付金を受け取ったら、手続きは完了です。
相続税還付に必要な費用や必要書類

相続税還付とは、相続税を納め過ぎた場合に、税務署から返金を受けることです。
相続税還付を受けるためには、相続税の更正の請求という手続きを行う必要があります。
ここでは、相続税還付に必要な費用や必要書類について解説します。
相続税還付に必要な費用
相続税還付に必要な費用は、主に以下の2つです。
- 税理士報酬
- 証拠書類の取得費用
税理士報酬
相続税還付の手続きは、相続税の申告と同様に、複雑で専門的な知識が必要です。
そのため、ほとんどの場合、税理士に依頼することになります。
税理士に依頼する場合、税理士報酬を支払う必要があります。
税理士報酬は、税理士事務所や依頼内容によって異なりますが、一般的には、還付金額の10~20%程度が目安となります。
ただし、還付金額が少額の場合や、手続きが簡単な場合は、固定料金での契約も可能です。
また、還付金が得られなかった場合は、報酬を減額することもあります。
税理士報酬は、還付金の振込後に支払うことが多いですが、事前に相談しておくことが大切です。
税理士に依頼する際は、報酬の額や支払い時期、支払い方法などを明確に確認し、契約書に記載しておきましょう。
証拠書類の取得費用
相続税還付の手続きでは、相続税の納税額が減る理由や根拠を明確に示す必要があります。
そのため、更正の請求の根拠となる証拠書類を添付する必要があります。
証拠書類の種類は、相続財産の内容や更正の請求の理由によって異なりますが、例えば、以下のようなものがあります。
- 土地の評価額を見直した場合:測量図、写真、不動産鑑定評価書など
- 相続財産の数や内容が間違っていた場合:遺言書、遺産分割協議書、預貯金通帳、株式証券など
- 相続税の計算方法や税率が間違っていた場合:計算式や税表の訂正など
- 相続税の特例や控除が適用されなかった場合:特例や控除の適用条件を満たすことを示す書類など
- 贈与税の相続時精算課税制度が適用されなかった場合:贈与契約書、贈与税の納税証明書など
これらの証拠書類の中には、公的機関や金融機関などから取得することが必要なものもあります。
その場合、取得には手数料や郵送費などがかかることがあります。
証拠書類の取得費用は、相続財産の内容や更正の請求の理由によって異なりますが、一般的には、数千円から数万円程度が目安となります。
相続税還付に必要な書類
相続税還付に必要な書類は、以下の3つです。
- 更正の請求書
- 証拠書類
- 還付金振込依頼書
更正の請求書
更正の請求書は、相続税の申告書と同じように、相続財産の評価額や相続税の計算方法などを記入します。
ただし、更正の請求をするに至った経緯や理由、還付金の振込先なども記入する必要があります。
また、更正の請求の根拠となる証拠書類も添付します。
更正の請求書は、税務署のホームページからダウンロードできます。
また、税理士に依頼する場合は、税理士が作成してくれます。
証拠書類
証拠書類は、相続税の納税額が減る理由や根拠を明確に示すために必要な書類です。
証拠書類の種類は、相続財産の内容や更正の請求の理由によって異なります。
証拠書類の例は、前述の「証拠書類の取得費用」の項目を参照してください。
還付金振込依頼書
還付金振込依頼書は、還付金を受け取るために必要な書類です。
還付金振込依頼書には、還付金の受取人の氏名や住所、還付金を振り込む口座の情報などを記入します。
還付金振込依頼書は、税務署のホームページからダウンロードできます。
また、税理士に依頼する場合は、税理士が作成してくれます。
相続税還付に必要な費用や必要書類について、以下のようにまとめることができます。
- 相続税還付に必要な費用は、税理士報酬と証拠書類の取得費用で、一般的には、還付金額の10〜20%程度と数千円から数万円程度が目安となる。
- 相続税還付に必要な書類は、更正の請求書、証拠書類、還付金振込依頼書で、税務署のホームページからダウンロードできる。税理士に依頼する場合は、税理士が作成してくれる。
相続税還付は、相続税の申告期限から5年以内に行う必要があります。
過去に多額の相続税を納めている方は、自分が相続税還付の対象になる可能性があるかどうか、税理士に相談してみると良いでしょう。
相続税還付の手続きは、相続税の申告と同じくらい難しく、時間もかかりますが、税理士のサポートを受けることで、スムーズに進めることができます。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続税還付のメリット

相続税還付とは、相続税を多く納めてしまった場合に、税務署から払い過ぎた分の税金を返してもらうことです。
相続税還付を受けるには、相続税の更正の請求という手続きを行う必要があります。
ここでは、相続税還付のメリットについて解説します。
相続税還付のメリットは、大きく以下の3つに分けられます。
- 払い過ぎた相続税が戻ってくる
- 相続財産を有効に活用できる
- 税務署とのトラブルを避けられる
払い過ぎた相続税が戻ってくる
相続税の還付による最大の利点は、手持ちの現金が増加することです。
相続税の最高税率が55%に達するため、一度の相続で多くの方が財産を大幅に失ってしまいます。
相続税還付を受けることで、払い過ぎた相続税額が返ってきますので、相続人の負担が軽減されます。
相続税還付の金額は、相続財産の内容や評価誤りの程度によって異なりますが、場合によっては数百万円から数千万円の還付が可能です。
相続財産を有効に活用できる
相続税還付を受けることで、相続財産を有効に活用できるというメリットもあります。
相続税を納めるために、相続財産の一部を売却したり、ローンを組んだりする方もいらっしゃいます。
しかし、相続税還付を受けることで、相続財産を売却する必要がなくなったり、ローンの返済が楽になったりすることがあります。
また、相続財産に不動産が含まれる場合は、相続税還付を受けることで、固定資産税や管理費などの負担が減ったり、賃貸や売却などの選択肢が広がったりすることがあります。
税務署とのトラブルを避けられる
相続税還付を受けることで、税務署とのトラブルを避けられるというメリットもあります。
相続税の申告は、相続人が自己申告する制度ですが、税務署は申告内容に不備や疑義があると判断した場合、申告書の訂正や追加の提出を求めたり、現地調査や聴取を行ったりすることがあります。
これを「相続税調査」と呼びます。
相続税調査は、相続人にとって時間や労力、精神的な負担が大きく、場合によっては税額の増加や罰則の適用などの不利益を被ることもあります。
相続税還付を受けることで、相続税の申告内容を正しく訂正することができますので、税務署とのトラブルを未然に防ぐことができます。
相続税還付とは、相続税を多く納めてしまった場合に、税務署から払い過ぎた分の税金を返してもらうことです。
相続税還付を受けるには、相続税の更正の請求という手続きを行う必要があります。
相続税還付のメリットは、払い過ぎた相続税が戻ってくること、相続財産を有効に活用できること、税務署とのトラブルを避けられることです。
相続税の還付されるケース

相続税の還付を受けるには、相続税の更正の請求という手続きを行う必要があります。
ここでは、相続税の還付されるケースの具体例について解説します。
相続税の還付されるケースは、主に以下のようなものがあります。
- 相続財産の評価額が間違っていた場合
- 相続税の計算方法や税率が間違っていた場合
- 相続税の特例や控除が適用されなかった場合
- 贈与税の相続時精算課税制度が適用されなかった場合
- 遺産分割協議や裁判などで相続財産の内容が変わった場合
- 相続人の数や相続分が間違っていた場合
- 相続財産に債務や負担があった場合
これらのケースでは、相続税の申告内容を訂正することで、相続税の納税額が減少する可能性があります。
その場合、払い過ぎた相続税の差額が還付されます。
相続財産の評価額が間違っていた場合
相続財産の評価額が間違っていた場合は、相続税の還付が発生する可能性が高いケースです。
相続財産の中でも、土地や建物などの不動産は評価方法が複雑で、専門的な知識が必要です。
しかし、相続税の申告を行った税理士が不動産の評価に慣れていなかったり、現地調査を行わなかったりすると、適切な評価額を算出できないことがあります。
その結果、相続財産の評価額が過大になり、相続税も多く納めてしまうことになります。
相続財産の評価額を見直すには、不動産鑑定士や土地家屋調査士などの専門家に依頼するのが望ましいです。
また、相続財産の評価額を見直す際には、相続開始時の時価を基準とします。
相続開始時とは、被相続人が亡くなった日のことです。
相続開始時の時価を証明するためには、不動産鑑定評価書や測量図、写真などの証拠書類が必要です。
これらの書類を更正の請求書に添付して、税務署に提出します。
相続税の計算方法や税率が間違っていた場合
相続税の計算方法や税率が間違っていた場合も、相続税の還付が発生する可能性があります。
相続税の計算方法や税率は、相続税法や国税通則法などの法律や通達に基づいて決まりますが、これらの法令は時々改正されることがあります。
そのため、相続税の申告を行った税理士が最新の法令に精通していなかったり、計算式や税表に誤りがあったりすると、相続税の計算方法や税率が間違ってしまうことがあります。
その結果、相続税も多く納めてしまうことになります。
相続税の計算方法や税率を見直すには、相続税の申告書に記載した計算式や税表を訂正する必要があります。
また、計算方法や税率を間違えた理由や根拠を明確に示す必要があります。
これらの内容を更正の請求書に記入して、税務署に提出します。
相続税の特例や控除が適用されなかった場合
相続税の特例や控除が適用されなかった場合も、相続税の還付が発生する可能性があります。
相続税の特例や控除とは、相続財産の評価額や相続税の納税額を減らすことができる制度のことです。
例えば、以下のようなものがあります。
- 家族信託の特例
- 遺族居住用財産の特例
- 事業承継の特例
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 障害者控除
- 寄付控除
これらの特例や控除は、一定の条件を満たす必要があります。
しかし、相続税の申告を行った税理士がこれらの条件を把握していなかったり、適用するために必要な書類を添付しなかったりすると、特例や控除が適用されないことがあります。
その結果、相続財産の評価額や相続税の納税額が高くなり、相続税も多く納めてしまうことになります。
相続税の特例や控除を見直すには、特例や控除の適用条件を確認し、適用できるものがあれば、相続財産の評価額や相続税の計算方法を訂正する必要があります。
また、特例や控除の適用に必要な書類を準備し、更正の請求書に添付して、税務署に提出します。
贈与税の相続時精算課税制度が適用されなかった場合
贈与税の相続時精算課税制度が適用されなかった場合も、相続税の還付が発生する可能性があります。
贈与税の相続時精算課税制度とは、相続人が被相続人から相続開始の3年以内に贈与を受けた場合、その贈与財産を相続財産に含めて相続税を計算する代わりに、贈与税を相続税から差し引くことができる制度のことです。
この制度は、相続税と贈与税の二重課税を防ぐ為のものです。
しかし相続税の申告を行った税理士がこの制度の存在を知らなかったり、適用するために必要な書類を添付しなかったりすると、贈与税の相続時精算課税制度が適用されないことがあります。
その結果、相続財産の評価額や相続税の納税額が高くなり、相続税も多く納めてしまうことになります。
贈与税の相続時精算課税制度を見直すには、相続人が被相続人から受けた贈与の内容や時期、贈与税の納税状況などを確認する必要があります。
また、贈与税の相続時精算課税制度の適用に必要な書類を準備し、更正の請求書に添付して、税務署に提出します。
必要な書類は、以下のようなものがあります。
- 贈与契約書
- 贈与税の納税証明書
- 贈与財産の評価額の証明書
相続税計画は、我々の生活において重要な役割を果たします。 その中でも、特に注目すべきは贈与税の課税制度の選択です。 本記事では、相続時精算課税制度について以下の点を中心にご紹介します! 相続時精算課税制度 相続時[…]
遺産分割協議や裁判などで相続財産の内容が変わった場合
遺産分割協議や裁判などで相続財産の内容が変わった場合も、相続税の還付が発生する可能性があります。
相続財産の内容が変わるということは、相続人の相続分や相続財産の評価額が変わるということです。
そのため、相続税の申告時には、変更後の相続財産の内容に基づいて、相続税を計算する必要があります。
しかし、相続税の申告時には、遺産分割協議や裁判の結果が確定していなかったり、変更後の相続財産の内容を正しく把握していなかったりすると、相続税の計算が間違ってしまうことがあります。
その結果、相続税も多く納めてしまうことになります。
相続財産の内容が変わった場合は、相続税の申告書に記載した相続人の数や相続分、相続財産の評価額などを訂正する必要があります。
また、相続財産の内容が変わった理由や根拠を明確に示す必要があります。
これらの内容を更正の請求書に記入して、税務署に提出します。
必要な書類は、以下のようなものがあります。
- 遺産分割協議書
- 裁判の判決書
- 変更後の相続財産の評価額の証明書
相続人の数や相続分が間違っていた場合
相続人の数や相続分が間違っていた場合も、相続税の還付が発生する可能性があります。
相続人の数や相続分は、相続税の計算に大きく影響します。
相続人の数が多ければ多いほど、相続税の納税額は減少します。
また、相続分が小さければ小さいほど、相続税の納税額は減少します。
しかし、相続税の申告時には、相続人の数や相続分を正しく把握していなかったり、遺言書や遺産分割協議書などの書類を添付しなかったりすると、相続人の数や相続分が間違ってしまうことがあります。
その結果、相続税も多く納めてしまうことになります。
相続人の数や相続分を見直すには、相続税の申告書に記載した相続人の数や相続分を訂正する必要があります。
また、相続人の数や相続分を証明する書類を準備し、更正の請求書に添付して、税務署に提出します。
必要な書類は、以下のようなものがあります。
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 相続人の戸籍謄本
相続財産に債務や負担があった場合
相続財産に債務や負担があった場合も、相続税の還付が発生する可能性があります。
相続財産に債務や負担があるということは、相続財産の価値が減少するということです。
そのため、相続税の申告時には、債務や負担の額を相続財産の評価額から差し引く必要があります。
しかし、相続税の申告時には、債務や負担の存在や額を正しく把握していなかったり、債務や負担の証明書類を添付しなかったりすると、債務や負担の額を差し引かないことがあります。
その結果、相続財産の評価額が過大になり、相続税も多く納めてしまうことになります。
相続財産に債務や負担があった場合は、相続税の申告書に記載した相続財産の評価額を訂正する必要があります。
また、債務や負担の存在や額を証明する書類を準備し、更正の請求書に添付して、税務署に提出します。
必要な書類は、以下のようなものがあります。
- 債務の契約書
- 債務の残高証明書
- 負担の契約書
- 負担の支払い証明書
相続税還付の成功例と失敗例

ここでは相続税還付の成功例と失敗例について解説します。
相続税還付の成功例
相続税還付の成功例として、以下のようなケースがあります。
広大地の評価減額で還付
広大地とは、その地域における標準的な宅地の面積に比べて、かなり広い土地のことです。広大地は、一定の要件を満たすと、土地の評価額が最大65%減額されます。
しかし、広大地の評価減額は、相続税の申告時に適用されなかったり、正しく計算されなかったりすることがあります。
その場合、更正の請求で評価減額を受けることができます。
例えば、以下のような事例があります。
- 相続財産に、面積が1,000平方メートル以上の土地が含まれていた。
- 相続税の申告時に、広大地の評価減額が適用されなかった。
- 更正の請求で、広大地の評価減額が認められた。
- 相続税が3,000万円減額され、還付された。
不動産の形状や環境による評価減額で還付
不動産の形状や環境によっては、土地や建物の評価額を減額することができます。
例えば、以下のような場合が該当します。
- 不整形地:土地の形が正方形や長方形ではなく、利用価値が低い場合。
- 無道路地:土地が道路に面していない場合や、細い道を通って出入りする場合。
- 傾斜地:土地が平坦ではなく、傾斜がある場合。
- 線路沿い・高圧線下・忌み地など:土地の周囲の環境が悪く、騒音や振動、制限などがある場合。
- 庭内神祠:土地内に鳥居や祠などがある場合。
これらの場合は、相続税の申告時に評価減額の特例が適用されることがありますが、適用されなかったり、正しく評価されなかったりすることがあります。
その場合、更正の請求で評価減額を受けることができます。
例えば、以下のような事例があります。
- 相続財産に、不整形地や線路沿いの土地が含まれていた。
- 相続税の申告時に、評価減額の特例が適用されなかった。
- 更正の請求で、評価減額の特例が認められた。
- 相続税が1,000万円減額され、還付された。
相続税還付の失敗例
相続税還付の失敗例として、以下のようなケースがあります。
税務調査の誘発
更正の請求をすると、税務署から税務調査を受ける可能性があります。
税務調査とは、税務署が納税者の帳簿や書類を調べて、申告内容に誤りや不正がないかを確認することです。
税務調査が行われると、相続財産の評価額だけでなく、相続財産の範囲や相続人の関係なども検証されます。
その結果、相続税の還付を受けるために更正の請求をすると、税務署から税務調査を受ける可能性があります。
税務調査とは、税務署が納税者の帳簿や書類を調べて、申告内容に誤りや不正がないかを確認することです。
税務調査が行われると、相続財産の評価額だけでなく、相続財産の範囲や相続人の関係なども検証されます。
その結果、相続税の還付だけでなく、追加の納税や罰則の対象になることもあります。
例えば、以下のような事例があります。
- 相続財産に、相続人が知らなかった預貯金や株式などが含まれていた。
- 相続税の申告時に、これらの財産を申告漏れしていた。
- 更正の請求で、土地の評価減額を受けようとした。
- 税務調査で、申告漏れの財産が発覚した。
- 相続税が5,000万円増額され、罰金も課された。
更正の請求の注意点
更正の請求をする際には、以下の点に注意する必要があります。
- 更正の請求は、相続税の申告期限から5年以内に行わなければなりません。
5年を過ぎると、更正の請求ができなくなります。 - 更正の請求は、相続税の申告内容の訂正や減額の理由を明確に示さなければなりません。
曖昧な理由や根拠のない主張は、税務署に受理されません。 - 更正の請求は、相続財産の評価意見書や債務の証明書などの資料を添付しなければなりません。
資料が不十分だと、税務署に審査されません。 - 更正の請求は、税務調査の誘発を避けるために、専門家に依頼することが望ましいです。
専門家に依頼すると、相続税の申告内容の見直しや、評価意見書の作成などのサポートを受けることができます。
相続税還付とは、相続税の申告時に、過払いになった相続税を、税務署から返金してもらうことです。
相続税還付を受けるには、相続税の申告期限から5年以内に更正の請求という手続きを行う必要があります。
相続税還付の可能性がある土地として、広大地や不整形地などの評価減額の対象となる土地があります。
しかし、更正の請求をすると、税務調査を受けるリスクもあります。
そのため、更正の請求は、専門家に依頼することがおすすめです。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続税還付をするときの税理士の選び方
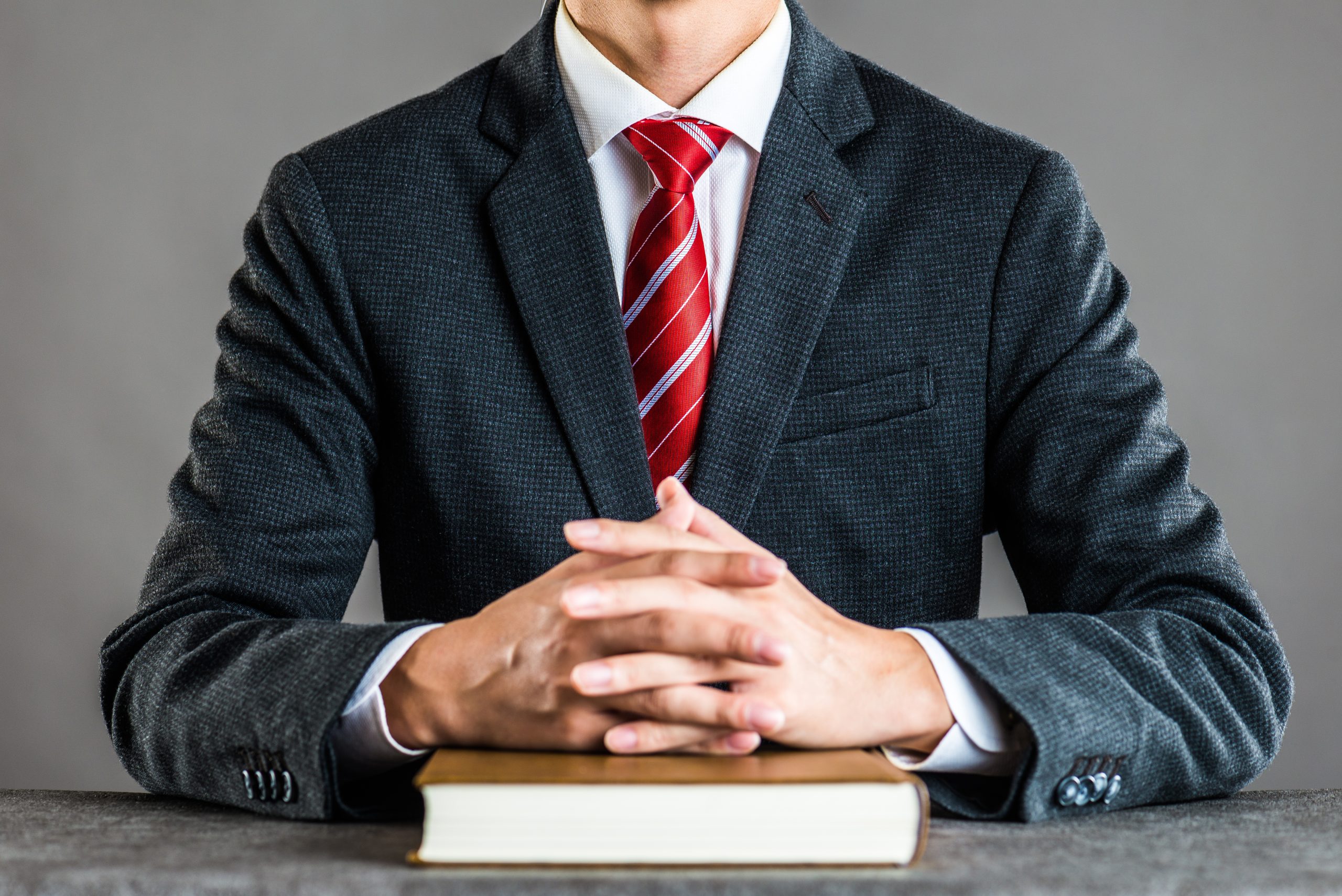
相続税還付とは、相続税の申告時に、過払いになった相続税を、税務署から返金してもらうことです。
相続税還付を受けるには、相続税の申告期限から5年以内に更正の請求という手続きを行う必要があります。
この手続きは、相続税に詳しい税理士に依頼することがおすすめです。
しかし、どのようにして相続税に強い税理士を見つけることができるのでしょうか?
ここでは、相続税還付をするときの税理士の選び方について、以下の4つのポイントを紹介します。
- 相続税の実績と還付の成功事例
- 不動産鑑定士との連携
- 報酬体系と費用
- 信頼性とコミュニケーション
相続税の実績と還付の成功事例
相続税還付の手続きは、相続財産の評価や相続税の計算など、専門的な知識と経験が必要です。
そのため、相続税に強い税理士を選ぶ際には、相続税の申告や還付の実績を確認することが重要です。
税理士のホームページやブログなどで、相続税の申告件数や還付件数、還付金額などのデータを公開しているかどうかをチェックしましょう。
また、具体的な相続税還付の成功事例やお客様の声なども参考になります。
相続税還付の可能性が高い土地の特徴や、還付のポイントなどをわかりやすく解説しているかどうかも、税理士の相続税の専門性やノウハウを判断する材料になります。
不動産鑑定士との連携
相続税還付の手続きでは、相続財産の中でも特に土地の評価が重要なポイントになります。
土地の評価は、不動産鑑定士という専門家に依頼することが一般的です。
不動産鑑定士は、土地の形状や利用状況、周辺環境などを考慮して、土地の評価意見書を作成します。
この評価意見書は、相続税還付の根拠となる重要な資料です。
そのため、相続税に強い税理士を選ぶ際には、不動産鑑定士との連携がスムーズにできるかどうかを確認することが必要です。
税理士と不動産鑑定士が協力して、土地の評価を適正に行うことで、相続税還付の確率や金額を高めることができます。
報酬体系と費用
相続税還付の手続きには、税理士報酬や不動産鑑定士報酬などの費用がかかります。
相続税に強い税理士を選ぶ際には、報酬体系や費用の明確さも重視することが必要です。
税理士報酬には、一律料金制や時間制、成功報酬制などがあります。
一律料金制や時間制は、事前に報酬額が決まっているので安心ですが、還付金額によっては割高に感じることもあります。
成功報酬制は、還付金額に応じて報酬額が変わるので、還付金額が少ない場合はお得ですが、還付金額が多い場合は高額になることもあります。
また、不動産鑑定士報酬やその他の経費も、税理士報酬に含まれているかどうかを確認することが必要です。
相続税還付の手続きにかかる費用は、税理士によって異なりますので、複数の税理士に見積もりを依頼して比較することがおすすめです。
信頼性とコミュニケーション
相続税還付の手続きは、相続税の申告内容の見直しや、税務署との交渉など、デリケートな内容が多く含まれます。
そのため、相続税に強い税理士を選ぶ際には、信頼性とコミュニケーションも重要なポイントになります。
信頼性とは、税理士が適切な資格や経験を持っているかどうか、税理士法人や税理士会などの団体に所属しているかどうか、税務署や不動産鑑定士との関係が良好かどうかなどを判断することです。
コミュニケーションとは、税理士が相続税還付の手続きの流れや内容をわかりやすく説明してくれるかどうか、相続人の疑問や要望に対応してくれるかどうか、連絡や報告がスムーズにできるかどうかなどを判断することです。
信頼性とコミュニケーションが高い税理士は、相続人の利益を最大限に守ってくれるでしょう。
相続発生後、慌ただしく進めなければならない手続きの数々です。 その中でも、特に重要となるのが「相続税申告」です。ご自身で申告することも可能ですが、遺産の内容によっては、税理士に依頼することも可能です。 ここでは、相続手続きにおけ[…]
相続税の還付制度についてのまとめ

ここまで相続税の還付制度についてお伝えしてきました。
相続税の還付制度の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続税の還付制度は、相続税の申告時に過払いになった相続税を、税務署から返金してもらう制度
- 相続税還付制度の手続きは、相続税の申告内容に誤りがあることを確認する、管轄税務署に更正の請求書と必要書類を提出する、税務署が請求内容を審査し、更正通知書を送付する、指定した口座に還付金が振り込まれる
- 相続税還付制度のメリットは、払い過ぎた相続税が戻ってくること
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




