土地を相続した場合、相続税がかかるのか気になりますよね。
この記事では、土地の相続税について、かかるのか、どういった計算方法で税額が決まるのか、どんな控除があるのかをわかりやすく解説します。
相続税について知りたい方は、ぜひご覧ください。
- 相続税対策とは
- 相続税とは
- 生前にしておくべき相続税対策
相続税の対策についてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続対策とは

相続対策とは、遺産相続に際して発生する相続税の負担を軽減するための準備や措置を指します。
相続税は、遺産の評価額に基づいて課税されるため、生前に財産を減らす対策が有効です。
具体的には、非課税の範囲内での贈与や生命保険の活用、不動産の有効利用などが挙げられます。
また、家族間のトラブルを防ぐ「争族対策」として、遺言書の作成や生前のコミュニケーションも重要です。
適切な対策を講じるためには、専門家の助言が欠かせません。
相続税とは

相続税とは、亡くなった方の遺産を受け取る人が納める税金です。
遺産の額や相続人の数、被相続人との関係などによって税額が決まります。
相続税については、こちらの記事もお読みください。
相続税は、多くの方にとって複雑で気になる要素の一つではないでしょうか。 特に、「相続税はいくらからかかるのか」という疑問は、相続に直面した際に非常に重要です。 この記事では、相続税はいくらからかについて以下の点を中心にご紹介します![…]
生前にしておくべき相続税対策

相続は誰にでも訪れる出来事ですが、相続税対策は早めに行っておくことが大切です。
以下では、相続税を軽減するために、生前にしておくべき対策をわかりやすく解説します。
年間110万円まで税金がかからない暦年贈与をする
暦年贈与は、相続対策として有効な手段の一つです。
毎年110万円までの贈与には税金がかからず、これを利用して計画的に財産を移転することができます。
この制度は、贈与税の非課税枠を活用して相続財産を減少させ、最終的に相続税の負担を軽減する効果があります。
ただし、贈与者が亡くなる直前の7年間に行われた贈与は、相続財産に加算されるため、早めの対策が重要です。
定期的な贈与による財産移転は、長期的に見て効果的な相続対策となります。
贈与税のかからない特例で贈与する
贈与税のかからない特例は、相続対策として活用できる重要な手段です。
例えば、教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与、住宅取得資金贈与の特例があります。
これらの特例を利用すると、一定額までの贈与が非課税となり、贈与者の財産を効果的に減らすことが可能です。
これにより、最終的な相続税の負担を軽減することができます。
しかし、特例の利用には期限があり、目的に沿った使途である必要があるため、注意が必要です。
贈与を計画的に進めることで、将来的な相続に向けた準備ができます。
相続税がかからない生命保険を契約する
相続税対策として、生命保険の活用は非常に有効です。
被保険者が生前に保険料を負担した場合でも、相続人が受取人であれば「500万円×法定相続人の数」までの保険金は非課税となります。
この制度を利用することで、相続人は相続税の支払いに必要な資金を確保でき、遺産分割に伴う負担を軽減できます。
ただし、非課税枠の適用には、受取人が相続人であることが条件です。
また、相続放棄を行った場合には、非課税枠は適用されない点に注意が必要です。
不動産を活用する
相続対策として、不動産の活用は効果的です。
特に賃貸用の不動産を所有する場合、その評価額は自宅や更地に比べて低く抑えられます。
これにより、相続税の評価額を引き下げることができます。
また、「小規模宅地等の特例」を活用すれば、賃貸事業用の土地に関しては一定の要件を満たすことで、評価額を最大で50%削減できます。
ただし、空き室がある場合や賃貸収入の増加に伴い、相続税の負担が増える可能性もあるため、適切な管理と計画が重要です。
不動産の有効活用により、相続税の節税が期待できます。
親子で同居する
親と同居することは、相続対策として有効な手段の一つです。
同居することで、相続する自宅の評価額を「小規模宅地等の特例」により、最大80%減額することができます。
この特例の適用には、被相続人の配偶者や同居親族が対象となります。
ただし、特例を利用するには相続開始後も住み続けることが条件です。
また、同居による生活の違いや価値観の相違がトラブルの原因になることもあるため、事前の話し合いが重要です。
この方法は、親の介護を行う家庭にとってもメリットが大きいです。
墓地や仏具などを生前に買って相続財産を減らす
相続対策として、墓地や仏具などを生前に購入する方法があります。
これらの祭祀財産には相続税がかからないため、生前に購入しておくことで相続財産を減らし、相続税の負担を軽減することが可能です。
ただし、これらの財産が礼拝用であることが前提であり、投資目的の場合には相続税がかかることに注意が必要です。
また、ローンでの購入は債務控除の対象とならないため、購入時の支払い方法についても考慮する必要があります。
この対策により、将来の相続税を減らすとともに、家族の負担を軽減することができます。
不動産の相続では、相続税の負担を軽減するための対策が重要です。 特例制度の活用や生前贈与、財産分割の工夫など、効果的な節税方法を知ることで、相続税を最小限に抑えることができます。 不動産の相続税対策について気になる方も多いのではない[…]
相続税対策で知っておくべきこと

相続は誰にでも訪れる出来事ですが、相続税対策は早めに行っておくことが大切です。
以下では、相続税対策で知っておくべきことをわかりやすく解説します。
基礎控除額を把握しておく
基礎控除額を理解することは、相続税対策の基本です。
相続税は、遺産全額にかかるのではなく、遺産総額から基礎控除額を引いた額にのみ課されます。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、遺産が基礎控除額以下の場合、相続税は発生しません。
たとえば、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4800万円となり、遺産が4500万円なら相続税はかかりません。
このため、相続人が自身の控除額を把握しておくことは重要です。
相続財産を減らすと相続税を抑えられる
相続財産を減らすことで相続税を軽減することが可能です。
これは、相続税は相続財産の総額に対して課せられるため、財産の総額を減らせばその分だけ課税対象額が少なくなるからです。
具体的な方法としては、基礎控除とは別に設けられた非課税枠の活用や、生前贈与による財産の分散が挙げられます。
また、現金を不動産などに変えることで、評価額を下げる手段もあります。
これにより、相続財産の評価額を低く抑え、相続税の負担を減らすことが可能です。
相続税評価額を下げることでも相続税を抑えられる
相続税評価額を下げることで相続税を抑える方法にはいくつかの手段があります。
相続税評価額とは、遺産の相続税計算に用いられる評価額で、これが高ければ高いほど相続税の負担も増します。
評価額を抑える方法の一つが、不動産や株式などの資産の評価方法を見直すことです。
例えば、土地の評価額は「路線価」や「固定資産税評価額」を基に決まりますが、適正な評価額を見直すことで税負担を軽減できる可能性があります。
また、相続税評価額を抑えるために、不動産の一部を譲渡する、あるいは生命保険の活用といった方法もあります。
生命保険の受取人を指定することで、保険金が相続財産から除外される場合があります。
これにより、相続財産が減少し、相続税の負担を軽減することができます。
相続税対策には専門家のアドバイスが重要であり、適切な方法を選択することで、相続税の負担を効果的に抑えることが可能です。
相続税対策の注意点
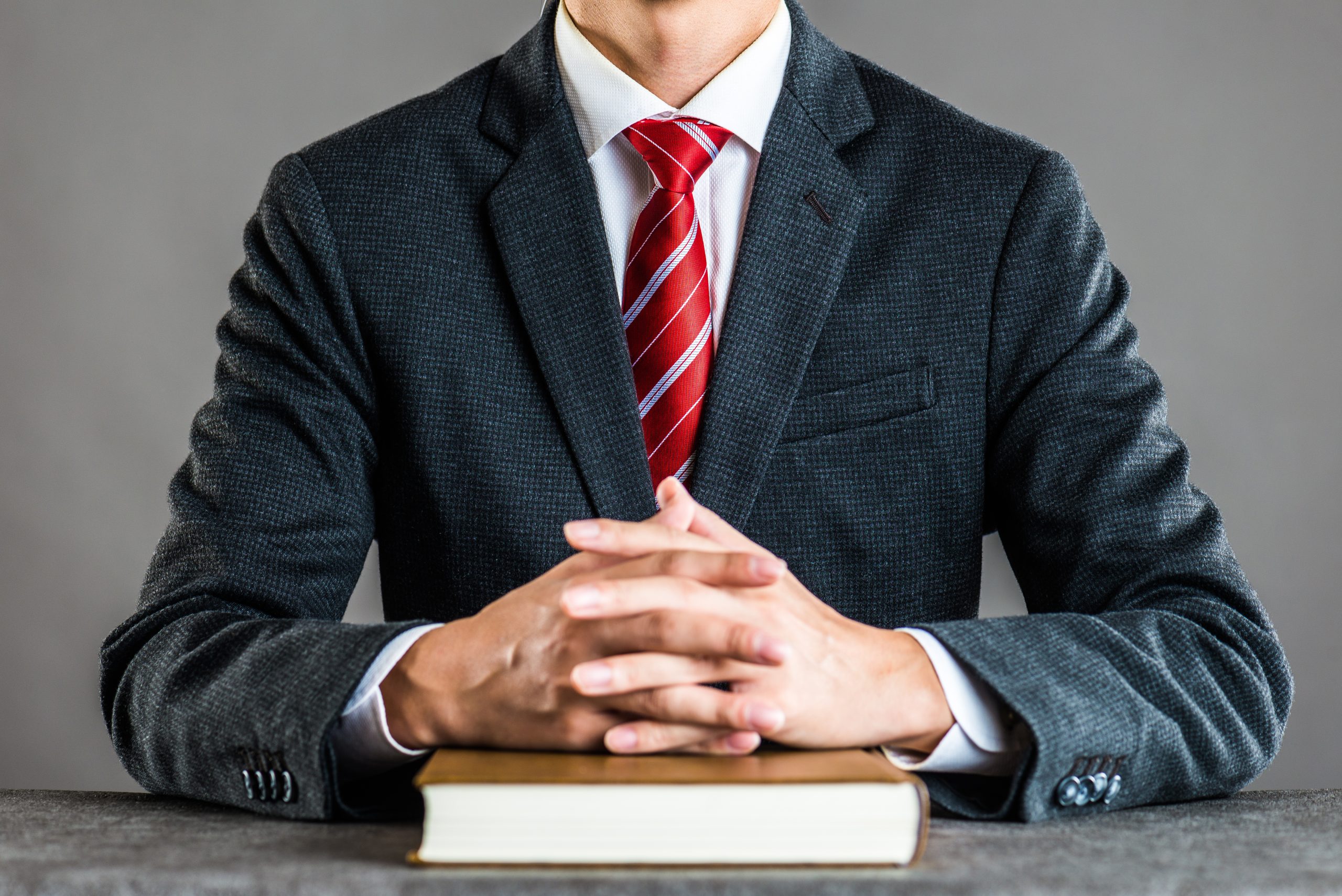
相続税対策は、早めに行うことで大きなメリットが得られますが、注意点も多く存在します。
以下では、相続税対策を行う際に必ず知っておくべき注意点をわかりやすく解説します。
過度な節税は否定されるリスクあり
過度な節税対策にはリスクが伴うことがあります。
節税目的で行われる過剰な対策は、税務署から不自然と見なされる可能性があり、結果として否定されるリスクが高まります。
例えば、相続税の軽減を狙って過度に複雑な資産分割や不自然な資産移転を行うと、税務調査で不正と見なされ、追徴課税や罰則が課されることがあります。
また、節税対策が法的に認められていない手法を用いると、後に大きな問題を引き起こすこともあります。
法律や税制に基づいた適切な節税策を講じることが重要であり、専門家の助言を受けながら計画的に行うことが求められます。
過度な節税は一時的な利益をもたらすかもしれませんが、長期的にはリスクを増大させる可能性があるため、注意が必要です。
老後資金とのバランスを考慮
老後資金とのバランスを考慮することは、資産管理において非常に重要です。
相続税対策や資産分割を進める際に、老後資金の確保を怠ると、将来的な生活の安定に影響を与える可能性があります。
例えば、相続税対策として資産を過度に分割したり譲渡したりすると、老後の生活資金が不足するリスクがあります。
そのため、相続税対策を講じる際には、老後の生活費や医療費などの必要資金を十分に考慮しながら計画を立てることが重要です。
バランスの取れた資産管理を行うことで、相続税対策と同時に老後の安心も確保できます。
専門家のアドバイスを受け、計画的に資産運用を行うことが、安心した老後生活とスムーズな相続の実現に繋がります。
家族同士が揉めない対策

相続は、家族の絆を試される出来事でもあります。
以下では、相続で家族がもめないための具体的な対策をご紹介します。
遺言をする
遺言を残すことは、相続に関する意向を明確にするために非常に重要です。
遺言を作成することで、自分の資産がどのように分配されるべきかを指定でき、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
例えば、遺言によって特定の資産を特定の人に遺贈することができるため、相続の際に予期しない争いが起こるリスクを減少させることができます。
また、遺言には法的な要件があるため、適切な形式で作成することが重要です。
自筆証書遺言や公正証書遺言など、遺言の形式によってその効力が異なるため、法律に従った正確な作成が必要です。
遺言の内容を定期的に見直し、変更が必要な場合には適切に対応することも、遺言の有効性を保つためには欠かせません。
遺言を通じて、自分の意志を確実に伝えることで、スムーズな相続を実現し、遺族に対する配慮も行うことができます。
生前のコミュニケーションで意思を伝える
生前にコミュニケーションを通じて自分の意思を伝えることは、相続における重要なステップです。
遺言や相続に関する意向を家族や親しい人々と共有することで、相続後のトラブルや誤解を防ぐことができます。
例えば、遺産の分配や特定の資産の扱いについて、事前に家族と話し合っておくことで、予期しない争いを未然に防ぐことができます。
また、生前のコミュニケーションは、遺言を作成する際の参考にもなります。
家族の意見や希望を把握することで、より具体的で実現可能な遺言内容を策定することができます。
さらに、これにより家族の理解と協力を得やすくなり、遺言執行時の円滑な進行が期待できます。
コミュニケーションを重ねることで、遺族に対する配慮を示し、スムーズで公正な相続を実現する手助けになります。
相続財産の一覧を作成する
相続財産の一覧を作成することは、スムーズな相続手続きを進めるために欠かせないステップです。
相続財産一覧には、不動産、預貯金、株式、保険などの資産だけでなく、負債やローンも含めて整理することが重要です。
これにより、相続時にどのような資産と負債が存在するのかを把握し、正確な相続税の計算や分配計画を立てることができます。
一覧作成の際には、各資産の評価額や所有権の情報を正確に記載することが求められます。
例えば、不動産の評価額や預貯金の残高、株式の銘柄や数量など、具体的な情報をまとめることで、相続人間での誤解を避けることができます。
また、定期的に一覧を見直し、変更があれば更新することで、最新の情報を保つことが可能です。
相続財産一覧の作成は、相続手続きの効率化を図り、トラブルを防ぐための重要な準備作業です。
生命保険に加入し、受取人を特定の子にする
生命保険に加入し、受取人を特定の子に指定することは、相続対策として有効な手段です。
生命保険の保険金は、受取人指定により、直接その受取人に支払われるため、相続財産として計上されず、相続税の負担軽減につながります。
例えば、保険金を特定の子に受け取らせることで、その子の相続分を調整することができ、全体的な相続のバランスを取る手助けになります。
さらに、生命保険の保険金は遺族にとって即時に手元に入る資金となり、相続手続きやその他の費用に充てることができます。
この方法により、相続人間での資産の公平な分配をサポートし、金銭的な負担を軽減することが可能です。
ただし、保険契約や受取人指定の内容については、専門家と相談し、法的な要件や手続きに従うことが大切です。
生命保険を賢く活用することで、円滑な相続と安心した遺族の生活支援を実現することができます。
相続手続きを進める上で、生命保険金は重要な財産の一つです。 しかし、生命保険金は、単純に相続財産に加算されるものではありません。 相続法には「特別受益」という概念があり、生命保険金がこれに該当する場合があります。本記事では、生命[…]
相続税の対策についてまとめ

相続税の対策についてお伝えしてきました。
相続税の対策についてまとめると以下の通りです。
- 相続対策とは、遺産相続に際して発生する相続税の負担を軽減するための準備や措置を指す
- 相続税とは、亡くなった方の遺産を受け取る人が納める税金を指す
- 生前にしておくべき相続税対策は、年間110万円まで税金がかからない暦年贈与をすることや贈与税のかからない特例で贈与する事が対策として挙げられる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




