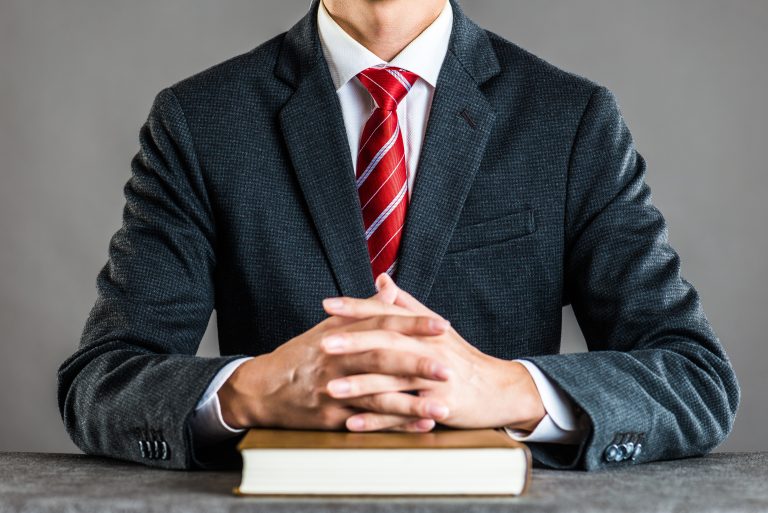法務局で遺言書を保管することについて気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、法務局で遺言書を保管することについて以下の点を中心にご紹介します!
- 法務局で遺言書を預ける制度について
- 法務局で遺言書を預ける手続き方法
- 他に遺言書を預けられるところ
法務局で遺言書を保管することについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
遺言書とは

遺言書とは、被相続人(故人)が自らの意思をもとに、死亡後の財産の分配方法や相続に関する希望を記した法的文書です。
遺言書があることで、法定相続分とは異なる財産の分配を希望する場合や、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書は、人生の最終章において個人が残すことのできる最も強力な法的文書の一つです。 これは、私たちがこの世を去った後に財産や大切な思い出がどのように扱われるかを定めるものであり、愛する方々への最後のメッセージとも言えます。 相続において[…]
遺言書の種類

遺言書には、作成方法や特徴が異なるいくつかの種類があります。
ここでは、代表的な自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を書いて作成する遺言書です。以下の特徴があります。
- 作成方法
遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。誤字や不備があると無効になる可能性があるため、正確に書くことが求められます。 - 費用
特別な費用はかからず、比較的簡単に作成できます。 - 注意点
保管場所に注意が必要です。紛失や改ざんのリスクがあり、相続時には家庭裁判所で検認手続きが必要となります。 - 改善点(財産目録の扱い)
2019年1月13日以降、財産目録部分はパソコンで作成したものや預金通帳のコピーを添付することが認められています。ただし、各ページに署名押印が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を基に作成する遺言書で、法的な有効性が高い形式です。以下の特徴があります。
- 作成方法
遺言者が2人以上の証人の立会いのもと、公証人に口述して作成します。公証人が遺言内容を筆記し、それを遺言者と証人に読み聞かせ、全員が署名押印します。 - 費用
公証人への手数料が必要ですが、形式に不備がなく、無効となるリスクが低いです。 - 保管
公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。 - 利点
相続時に家庭裁判所での検認手続きが不要で、迅速な相続手続きが可能です。
遺言書は、私たちが生涯を終えた後、自分の財産をどのように分配するかを決定する重要な文書です。 その中でも、「自筆証書遺言書」は、遺言者自身が直筆で書くことで法的な効力を持つ遺言の形式です。 しかし、その作成には特定の要件が必要で[…]
筆証書遺言書とは

証書遺言書は、遺言者が自らの意思を明確に記し、法的効力を持たせるために作成する遺言書の一種です。
証書遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
それぞれ特徴や作成方法が異なるため、遺言内容や目的に応じて適切な形式を選択することが重要です。
法務局の役割について

法務局は、主に不動産登記や商業登記などの公的な手続きの管理を行う機関ですが、遺言書に関しても重要な役割を果たしています。
特に、自筆証書遺言書の保管制度をはじめとして、遺言書の安全な保管や相続手続きの円滑化に関わる重要な業務を行っています。
1. 自筆証書遺言書の保管制度
法務局は、遺言者が作成した自筆証書遺言書を安全に保管する制度を提供しています。
この制度により、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、相続人が遺言内容を確認できるようになります。
具体的には、遺言者が法務局に遺言書を預けることで、遺言書の保管が行われ、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きを省略することができます。
- 遺言書の安全な保管
法務局で遺言書を保管することにより、紛失や改ざんのリスクを減少させることができます。 - 相続手続きの円滑化
相続人は遺言者の死亡後、法務局から通知を受けて遺言書を確認でき、相続手続きをスムーズに進めることができます。
2. 遺言書の保管申請手続き
法務局では、遺言者が自筆証書遺言を保管するための手続きを行います。
遺言者は、法務局に事前予約をし、必要書類を整えて申請を行います。
手続きが完了すると、法務局から遺言書の保管証が交付されます。
この手続きを利用することで、遺言書が法的に有効であることが保証され、相続時にトラブルを避けることができます。
3. 相続手続きの支援
法務局は、遺言書の保管だけでなく、相続登記に関する手続きもサポートします。
相続が発生した際、遺言書を基にした登記や財産分配が行われるため、法務局はその重要な役割を担っています。
また、遺言書の内容に基づいて遺産の名義変更などが行われます。
法務局は、遺言書の保管や相続手続きの円滑化を通じて、相続に関わる重要な手続きを支えています。
遺言書を安全に保管したい場合や相続に関するサポートが必要な場合は、法務局に相談することが重要です。
筆証書遺言書を保管する制度

自筆証書遺言書を法務局に保管する制度は、遺言者が作成した遺言書を安全に保管し、紛失や改ざんのリスクを防ぐために設けられた仕組みです。
この制度を利用することで、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが不要になり、相続手続きが円滑に進む利点があります。
筆証書遺言書を預ける方法
遺言書の作成
- 遺言者が自筆証書遺言書を作成します。
- 用紙サイズや余白など、所定の様式に従って作成してください。
法務局への事前予約
- 遺言書を保管するためには、管轄の法務局に事前予約が必要です。
- 予約はインターネットや電話を通じて行うことができます。
法務局での手続き
- 予約日時に法務局を訪問し、申請手続きを行います。
- 手続きが完了すると、「保管証」が交付されます。
- 保管された遺言書は、法務局で安全に保管され、相続人等が遺言者の死亡後に閲覧することができます。
筆証書遺言書を預けるために必要な書類
遺言書を保管する際には、以下の書類を準備してください。
- 保管申請書
- 必要事項を記載した申請書を用意します。
- 自筆証書遺言書
- 自ら作成した遺言書を提出します。
- 書式や内容に問題がある場合、受付が拒否されることもあるため、事前に内容を確認することをおすすめします。
- 本人確認書類
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの身分証明書を用意してください。
- 住民票の写し
- 遺言者本人の住民票の写しが必要です。
- 手数料(収入印紙)
- 手続きに必要な手数料は、収入印紙で納付します。
遺言書は、私たちが生涯を終えた後、自分の財産をどのように分けるかを決定する重要な文書です。 しかし、遺言書を作成し、それを安全に保管することは、多くの人々にとって難しい課題となっています。 そこで、日本の法務局が提供する「自筆証書遺[…]
筆証書遺言書を預けるためにかかる費用

法務局で自筆証書遺言書を保管する際には、手続きにかかる費用があります。
この費用は、遺言書の安全な保管と相続手続きの円滑化のためのものです。
1. 保管手数料
自筆証書遺言書の保管には、以下の費用が必要です。
- 手数料:1通につき3,900円(収入印紙で納付)
この費用は、保管申請時に法務局で支払います。
2. その他の費用(場合によって必要)
- 住民票の写し取得費用
保管申請には、遺言者本人の住民票の写しが必要です。住民票の発行には、1通あたり数百円の手数料がかかります(自治体によって異なります)。 - 交通費
法務局での申請手続きのために、法務局への往復交通費がかかる場合があります。
3. 費用の内訳の一例
例えば、1通の自筆証書遺言書を法務局に保管する場合の費用は以下のようになります。
| 項目 | 金額 |
| 保管手数料 | 3,900円 |
| 住民票の写し費用 | 約300~500円 |
| 交通費 | 個別に異なる |
費用に関する注意点
- 保管手数料は1通ごとに必要です。複数の遺言書を保管する場合は、その通数分の手数料がかかります。
- 手続きが完了した後の保管期間については、追加費用が発生することはありません。
- 遺言書の内容や形式に不備があると受付が拒否される場合があるため、内容を事前に確認しておくことをおすすめします。
法務局の保管制度を活用することで、遺言書の安全な保管が可能となり、相続人がスムーズに手続きを進めるためのメリットがあります。
費用については、事前に準備して手続きを行いましょう。
筆証書遺言書保管制度に関して相続人がする手続き

遺言者が自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合、相続人は遺言者の死亡後に適切な手続きを行うことで遺言書の内容を確認し、相続手続きを進めることができます。
1. 遺言書情報証明書の請求
相続人は遺言者が死亡したことを証明する書類を用意し、法務局に対して「遺言書情報証明書」の交付を請求します。
この証明書により、遺言書の内容を確認することが可能です。
必要書類:
- 遺言者の死亡を証明する書類(例:死亡診断書、戸籍謄本など)
- 請求者の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 遺言書保管所の所在地や遺言者の情報
手数料:
- 証明書1通につき1,400円(収入印紙で納付)
2. 遺言書の閲覧申請
相続人が遺言書の原本を確認したい場合、法務局で遺言書の閲覧を申請することができます。
これにより、遺言書の詳細を直接確認することが可能です。
必要書類:
- 遺言書情報証明書の請求時と同様の書類
3. 遺言書の内容に基づいた手続き
遺言書情報証明書の内容をもとに、遺産分割や相続登記などの手続きを進めます。
この段階で遺言執行者が指定されている場合、執行者が中心となって手続きを行います。
4. 注意点
- 法務局から遺言書保管の通知があった場合でも、相続人自身で内容確認のための手続きを行う必要があります。
- 遺言書が無効とされる要因(形式不備など)がないか確認するため、内容については専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをおすすめします。
この制度を活用することで、遺言書の検認手続きを省略し、スムーズに相続手続きを進めることができます。
適切な書類を準備し、法務局での手続きを確実に行いましょう。
遺言書の保管場所・保管方法

遺言書は相続における重要な文書であり、適切な保管が求められます。
不適切な保管は紛失や改ざん、無効になるリスクを高めるため、以下のような方法で保管することが推奨されます。
1. 自宅での保管
- メリット
- 自由に取り出せるため、遺言書をいつでも確認・修正しやすい
- 保管に費用がかからない
- 注意点
- 紛失や盗難、改ざんのリスクがある
- 遺言書の存在を相続人が知らない場合、発見が遅れる可能性がある
推奨ポイント:耐火性の金庫や特定の場所に保管し、信頼できる家族に場所を伝えておく
2. 法務局での保管(自筆証書遺言書保管制度)
- 特徴
- 遺言者が法務局に自筆証書遺言書を預ける制度
- 紛失や改ざんのリスクを防ぎ、家庭裁判所での検認手続きが不要になる
- 手続き
- 事前予約を行い、必要書類を揃えて法務局で申請
- 保管手数料は3,900円(収入印紙で納付)
- メリット
- 安全性が高く、法的に有効性が保たれる
- 遺言者の死亡後、相続人が容易に内容を確認できる
3. 公証役場での保管(公正証書遺言)
- 特徴
- 公証人が作成し、公証役場で保管されるため、高い安全性と法的有効性がある
- 遺言者の死亡後、相続人は公証役場で遺言書を受け取れる
- メリット
- 紛失や改ざんのリスクがほぼゼロ
- 作成時に公証人が関与するため、形式不備がない
4. 信託銀行での保管
- 特徴
- 一部の信託銀行では、遺言書の保管サービスを提供している
- プランにより遺言執行や相続手続きの代行も可能
- メリット
- 専門的な管理とサービスを受けられる
- 相続時のトラブルを防ぎやすい
- 注意点
- 保管費用がかかる(契約内容による)
保管方法選びのポイント
- 遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言)に適した保管方法を選ぶ
- 紛失や改ざんのリスクを防ぐため、安全性の高い場所を選ぶ
- 相続人や信頼できる第三者に保管場所を伝えておく
適切な保管場所と方法を選ぶことで、遺言書の効力を確実に保ち、円滑な相続手続きが実現します。
専門家への相談も活用して、安全で安心な保管を心がけましょう。
法務局で遺言書を保管することに関するよくある質問

遺言書を法務局に預ける方法は?
自筆証書遺言書を法務局に預けることで、紛失や改ざんのリスクを防ぎ、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
以下に預ける手順を説明します。
1. 遺言書の作成
- 自筆証書遺言書は、遺言者が全文を自書し、日付と署名を記入、押印したものでなければなりません。
- 形式不備があると受理されないため、法的な要件を確認してください。
2. 保管申請の予約
- 保管を希望する法務局に事前予約を行います。
- 予約は、法務局のウェブサイトまたは電話で受け付けています。
- 予約時に必要事項(遺言者の名前や希望日時など)を伝えます。
3. 必要書類の準備
法務局で保管手続きを進める際、以下の書類を揃える必要があります。
- 遺言書本体
保管を希望する自筆証書遺言書 - 保管申請書
法務局で入手またはダウンロードできます。 - 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど - 住民票の写し
遺言者本人の現住所を確認できるもの - 手数料(収入印紙)
1通につき3,900円を用意します。
4. 法務局での手続き
- 予約した日時に法務局を訪問します。
- 必要書類を提出し、内容が法的要件を満たしているかの確認を受けます。
- 手続きが完了すると、「保管証」が交付されます。これにより、遺言書は正式に法務局に保管されます。
5. 注意点
- 保管手続き後、遺言書の内容を変更したい場合は、新たに遺言書を作成し、再度申請が必要です。
- 法務局では遺言書の内容に関する相談やアドバイスは行っていないため、必要に応じて専門家に相談してください。
遺言書を自宅で保管することは可能?
遺言書を自宅で保管することは法律上可能です。
ただし、自宅で保管する際にはいくつかの注意点があります。
自宅保管のメリット
- 自由にアクセスできる
遺言者が自由に保管場所を選び、いつでも内容を確認したり修正したりできます。 - 費用がかからない
法務局や信託銀行などで保管する場合に必要な手数料が不要です。
自宅保管の注意点
- 紛失や改ざんのリスク
自宅で保管する場合、第三者による改ざんや紛失のリスクがあります。火災や災害による損失の可能性も考慮する必要があります。 - 存在の周知が重要
遺言書があることを家族や信頼できる人に周知しておかないと、遺言書が発見されないまま相続手続きが進む可能性があります。 - 検認が必要
自宅で保管された自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。この手続きには時間と費用がかかります。
自宅保管の推奨方法
- 安全な保管場所を選ぶ
耐火性の金庫やロッカーなど、改ざんや紛失のリスクが低い場所に保管しましょう。 - 信頼できる人に伝える
遺言書の保管場所を家族や信頼できる第三者に知らせておくことが重要です。 - 複数のコピーを作成
原本を安全な場所に保管し、必要に応じてコピーを家族に渡すことで、存在を確実に認識してもらえます。
専門家のサポートを検討
自宅で保管する際のリスクを軽減するために、専門家(弁護士や司法書士)に相談し、形式や内容に問題がないか確認することをおすすめします。
自宅保管は費用がかからず手軽ですが、紛失や改ざん、相続時のトラブルのリスクを考えると、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用することも一つの選択肢です。
それぞれの方法のメリット・デメリットを理解し、最適な保管方法を選びましょう。
法務局で遺言をするにはいくらかかる?
法務局で自筆証書遺言を保管する際には、以下の費用が必要となります。
1. 保管手数料
- 保管申請時に1通あたり3,900円の手数料がかかります。
- 手数料は収入印紙で納付する必要があります。
2. 関連するその他の費用(必要に応じて)
- 住民票の写し取得費用
遺言者本人の住民票が必要で、その発行手数料が発生します(1通あたり約300~500円、自治体により異なる)。 - 交通費
法務局への往復の交通費
3. 費用に含まれない内容
- 法務局では遺言書の内容のチェックや法律相談は行いません。
そのため、内容の確認やアドバイスが必要な場合は、別途弁護士や司法書士などの専門家に依頼する必要があります。
これには追加の相談料や手数料がかかる場合があります。
合計費用の目安
例えば、1通の自筆証書遺言を法務局に保管する場合の費用は以下のようになります。
| 項目 | 金額 |
| 保管手数料 | 3,900円 |
| 住民票の写し費用 | 約300~500円 |
| 交通費 | 個別に異なる |
経済的なメリット
法務局で遺言書を保管することで、紛失や改ざんのリスクを防ぎ、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きを省略できるため、結果的に手続き全体の効率が向上し、トラブルの防止につながります。
法務局の制度を活用することで、費用対効果の高い遺言書の保管が可能です。
法務局で遺言書を保管することについてのまとめ

ここまで法務局で遺言書を保管することについてお伝えしてきました。
法務局で遺言書を保管することの要点をまとめると以下の通りです。
- 自筆証書遺言書を法務局に保管する制度は、遺言者が作成した遺言書を安全に保管し、紛失や改ざんのリスクを防ぐために設けられた仕組み
- 遺言書の作成や法務局への事前予約など順番に進めていく
-
自宅で保管することや信託銀行での保管も可能
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。