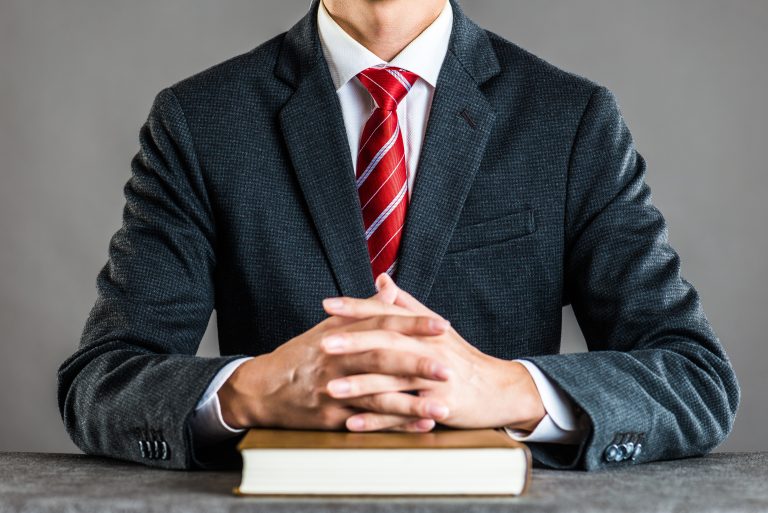相続登記は、亡くなった方の不動産を相続人の方に名義変更する手続きです。
スムーズな手続きのために、管轄の法務局を正しく理解することが重要です。
ここでは、相続登記はどこの法務局でもできるのかについて、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
- 相続登記は法務局に申請すべき?
- 法務局への申請前にやることは?
- 法務局で相続登記を行う際の注意点とは?
相続登記はどこの法務局でもできるのかについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続登記は法務局に申請

相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人に移転する手続きです。
これは、法務局という公的機関に申請する必要があります。
法務局は、全国各地に存在する役所で、不動産や自動車などの登記を扱っています。
相続登記を行う場合は、まず管轄の法務局を特定する必要があります。
相続登記はどこの法務局でもできる?

相続登記は、被相続人が所有していた不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があります。
複数の不動産を所有していた場合は、それぞれ管轄の法務局に申請する必要があります。
管轄法務局を間違えると、登記申請が却下される可能性があるので注意が必要です。
各法務局の管轄区域は、法務局のホームページなどで確認できます。
法務局への申請前にやることは?

申請しようとすると、必要な書類や手続きがわからず、戸惑ってしまうことも多いでしょう。
そこで、ここでは、法務局への申請前にやるべきことを、わかりやすくご説明します。
相続する不動産を確認する
亡くなった方が所有していた不動産の大半は、毎年4月頃に送付される固定資産税納税通知書に記載されています。
通知書には、不動産の所在地や地番、家屋番号などが記載されているので、これを参考に相続する不動産を確認することができます。
固定資産税が非課税である公衆用道路などの不動産は、固定資産税納税通知書に記載されていません。
このような不動産を確認するには、市区町村役場で発行している「名寄帳」を確認する方法があります。
名寄帳には、被相続人が所有していた不動産がすべて記載されているので、漏れなく確認することができます。
亡くなった方が不動産を購入した際に交付された権利証も、相続する不動産を確認する手掛かりになります。
権利証には、不動産の所在地や地番、家屋番号などが記載されているので、登記簿謄本と合わせて確認することで、より詳細な情報を得ることができます。
引き継ぐ人を決める
遺言書がある場合は遺言書の内容通りに遺産を分配します。
不動産も遺言書で指定された人が取得します。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議で誰が何を取得するかを決めます。
法定相続分による分割の場合は、法律で定められた相続割合で、遺産を相続人全員の共有名義にすることもできます。
話し合いは不要ですが、後々の売却や共有持分の相続手続きが煩雑になるため、あまりおすすめの方法ではありません。
法務局で相続登記手続きが行える方とは

不動産の名義を相続人に移転するには、法務局で相続登記手続きを行う必要があります。
この手続きは、基本的に「相続人本人」か「代理人」です。
相続人本人
基本的には、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」は、相続人本人が申請します。
法務局へ必要書類を提出するだけで完了しますが、ご自身で手続きを進めるのが不安な場合は、親族の方がサポートすることもできます。
司法書士に依頼
ご自身で対応するのが難しい場合は、登記のプロである司法書士に依頼するのが一般的です。
以下でメリットとデメリットをみていきましょう。
司法書士に依頼するメリット
確実かつスピーディーな相続登記が可能
- 書類作成、登録免許税の計算など、必要な手続きをすべて司法書士が行うので、ミスなくスムーズに相続登記を進めることができます。
- 相続人間で協議がまとまっている場合は、1ヶ月程度で手続きを完了させることも可能です。
時間と手間を節約できる
- 法務局への来訪や手続きに関する調査などは司法書士が行うので、相続人の方々が時間をかける必要はありません。
- 相続手続きは煩雑な書類作業や調査が必要となるため、特に仕事が忙しい方にとって大きなメリットとなります。
登記漏れのリスクを回避できる
- 司法書士は専門家として最新の法令に基づいた手続きを行うため、登記漏れのリスクを減らすことができます。
- 万が一登記漏れが発生した場合でも、司法書士であれば速やかに対応することができます。
遺産分割協議のサポートを受けられる
- 司法書士の中には、遺産分割協議に関する相談やアドバイスも行っているところがあります。
- 相続人間で揉めてしまっているような場合でも、公平かつ中立的な立場からアドバイスを受けることで、円滑な遺産分割協議を進めることができます。
司法書士に依頼するデメリット
費用がかかる
- 司法書士に依頼する場合は、報酬を支払う必要があります。
- 報酬は、相続財産の価額や必要な手続きの内容によって異なりますが、一般的には8万円~15万円程度です。
- ただし、確実に登記を完了できることや、時間と手間を節約できることを考えると、費用に見合った価値があると言えるでしょう。
親族に委任
相続人本人が手続きを行うことが困難な場合や、費用を抑えたい場合は、親族に代理で手続きを依頼することができます。
親族に相続登記を委任するには、委任状を作成する必要があります。
相続登記の申請方法

慣れていない手続きでは、何から始めればいいのか、どんな書類が必要なのか、わからないことも多いでしょう。
そこで、相続登記の申請方法をわかりやすくご説明します。
法務局の窓口で申請する
登記申請は、管轄の法務局へ直接出向いて行うことが最も確実かつ迅速な方法です。
通常、約10日前後で完了します。
申請に必要なもの
- 登記申請書(法務局で配布またはダウンロード可)
- 必要書類(登記の種類によって異なる)
- 登録免許税
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 申請書に押印した印鑑
郵送による申請
申請書と添付書類一式を書留郵便で送付します。
返信用封筒(本人限定郵便)を同封することを忘れないでください。
詳しくは、管轄法務局のホームページで確認できます。
オンラインでの申請
事前に申請環境を整える必要があります。
1回きりの申請のために時間と労力を費やすのは、ややハードルが高いかもしれません。
相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用は、大きく分けて3つあります。
- 登録免許税
- 司法書士報酬(依頼する場合)
- 必要書類取得費用
登録免許税
土地や建物の価額に対して、0.4%の税金を納める必要があります。
登録免許税は、相続登記申請時に収入印紙で購入して納めます。
例:
- 土地・建物の固定資産評価額が1,000万円の場合:登録免許税=1,000万円×0.4%=4万円
- 土地・建物の固定資産評価額が3,000万円の場合:登録免許税=3,000万円×0.4%=12万円
相続人が相続登記をしないで死亡した場合は、一定の条件を満たせば登録免許税が免除される特例措置があります。
合計費用目安
相続登記にかかる合計費用の目安は以下の通りです。
- 自分で手続きを行う場合:数千円~3万円程度
- 司法書士に依頼する場合:7万円~18万円程度
費用を抑えるポイント
- 自分で手続きを行う
- 相続人全員で協力して手続きを進める
- 複数の司法書士から見積もりを取る
相続登記は、遺産分割協議や相続税申告など、他の相続手続きと関連している重要な手続きです。
費用や手続き方法について不安な点があれば、法務局や司法書士に相談することをおすすめします。
法務局から指摘されやすい書類不備のポイント

せっかく用意した書類が不備で返却されてしまうと、手続きが遅れてしまいます。
ここでは、法務局から指摘されやすい書類不備のポイントをいくつかご紹介します。
誤字脱字
特に、登記名義人の氏名や住所、法人の名称や所在地など、重要な情報の誤字脱字は致命的です。
提出前に必ず誤字脱字がないか確認しましょう。
不備な記入
欄外に記入すべき事項を本文に記入したり、逆に本文に記入すべき事項を欄外に記入したりするなど、記入方法を間違えているケースも指摘されます。
各欄の使用方法をよく確認してから記入しましょう。
欠漏れ
署名・捺印、添付書類など、必要なものが欠けている場合も指摘されます。
チェックリストなどを活用して、必要なものが全て揃っていることを確認しましょう。
不鮮明な書類
コピーが薄かったり、汚れやシワがあったりして、内容が読み取れない書類は提出できません。
きれいな状態の原本を提出しましょう。
不適切なサイズ
法務局で定められているサイズよりも大きい書類や小さい書類は提出できません。
事前に法務局のホームページなどで確認しておきましょう。
相続登記の申請についてよくある質問

相続登記は必要書類も多く、手続きも複雑で、何をすればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
相続登記について少しでも理解を深め、スムーズな手続きを進めていただくために、ぜひご参考ください。
相続登記は自分でできる?
法務局に必要書類を提出することで、被相続人の名義だった不動産を相続人の名義に変更することができます。
相続登記を自分で行うメリット
- 司法書士に支払う報酬を節約できる
- 自分自身で手続きを進めることで、相続について理解を深めることができる
相続登記を自分で行うデメリット
- 手続きに手間と時間がかかる
- 間違いがあると登記簿に反映されないことがある
- 相続人間で揉めている場合は、自分で手続きを進めることが難しい
相続登記の義務化とは?罰則もある?
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。
これは、相続により不動産を取得した相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないことを意味します。正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
対象者は、相続により不動産を取得した相続人や遺産分割によって不動産を取得した相続人です。
施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
法務局で相続登記を行う際の注意点

適切な知識と準備があれば、スムーズな相続登記が可能です。
そこで今回は、法務局での相続登記を成功させるために、絶対に知っておくべき注意点を詳しく解説します。
土日祝日は基本的に手続きできない
相続登記は、法務局へ申請を行う手続きとなりますが、法務局は平日のみ開所しているため、土日祝日は基本的に相続登記の手続きを行うことができません。
相続登記には、必要書類の取得、申請、相談など、法務局以外にも自治体窓口での手続きも必要となります。
これらの窓口も平日のみ開所している場合がほとんどです。
さらに、法務局から申請書類の確認や修正依頼などの連絡が平日に入る場合もありますので、平日に電話対応できる環境も必要となります。
法務局での相続登記を自分で行う場合は、上記のような点を考慮し、平日の4~5日程度まとまった時間を取れるようにしておくことが重要です。
もし、平日にまとまった時間が取れない場合は、司法書士などの専門家に依頼することを検討しましょう。
司法書士は、土日祝日でも相談を受け付けている場合が多く、平日に時間を取れない方でもスムーズに相続登記を進めることができます。
相続登記を行わないと罰則が課せられることがある
所有者不明土地の増加対策として、相続登記が義務化されました。
相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を、相続人に変更する手続きです。
これまで任意だったのですが、2024年4月1日からは、相続財産に不動産が含まれる場合は、相続人全員が3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。
放置された相続登記は、所有者が分からなくなり、土地の利用や管理が困難になるだけでなく、災害時の救助や復興の妨げにもなります。
受付番号は必ず控えておく
相続登記を行うと、法務局によって受付年月日と受付番号が発行されます。
この番号は、登記申請に関する問い合わせや登記の取り下げを行う際に必要となります。
法務局へ登記申請に関する問い合わせを行う場合や、登記の取り下げが必要となった場合は、必ず受付年月日と受付番号を伝える必要があります。
受付番号を控えていない場合、本人確認が困難となり、手続きが進まなくなる可能性があります。
また、再発行には時間がかかったり、手数料が発生したりする可能性もあります。
原本還付請求を行う
相続登記で必要となる戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産税評価証明書などの書類は、原本を提出する必要があります。
しかし、原本還付請求をすることで、登記完了後に原本を返してもらうことができます。
原本を返却してもらうことで、他の相続手続きでも再発行の手間が省けます。
特に、遺産分割協議書は原本が必要となる手続きが多いので、原本還付請求がおすすめです。
相続登記はどこの法務局でもできるのかについてまとめ

ここまで相続登記はどこの法務局でもできるのかについてお伝えしてきました。
相続登記はどこの法務局でもできるのかをまとめると以下の通りです。
- 相続登記を行う場合は、法務局という公的機関に申請する必要がある
- 法務局への申請前にやるべきことは、相続する不動産を確認するや、引き継ぐ人を決めることが挙げられる
- 法務局で相続登記を行う際の注意点は、土日祝日は基本的に手続きできないことや相続登記を行わないとや罰則が課せられることがあることが挙げられる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。