不動産を相続したとき、名義変更の手続きを自分で行えるのか疑問に思う方も多いのではありませんか?
専門家に依頼すると費用がかかりますが、自分で手続きを進めればコストを抑えることができます。
本記事では不動産相続の名義変更が自分で行えるのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 不動産相続による名義変更とは
- 不動産相続の名義変更を自分で行う手順
- 不動産相続の名義変更にかかる費用
不動産相続の名義変更が自分で行えるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
不動産相続による名義変更とは?

不動産相続に伴う名義変更は、不動産の所有者が亡くなった際に、その権利を相続人に引き継ぐために行う重要な手続きです。
不動産に関する情報は、その所在地を管轄する法務局で管理されており、種類や用途、面積、権利者などが詳細に記録されています。
この記録を証明する書類が「登記事項証明書」で一般的には「登記簿謄本」として知られています。
不動産の所有者に変更が生じた場合には、この記録を更新する必要があります。
相続が発生した場合も同様に、相続人が新しい所有者として名義変更を申請する手続きが必要です。
この手続きを「相続登記」と呼びます。
相続登記を行うことで、法的に相続人が不動産の新たな所有者であることが認められます。
2024年4月1日からの法改正により、相続登記が義務化されました。
これにより、相続登記は「不動産の所有権を取得したと認識した日から3年以内」に行わなければなりません。
正当な理由がないまま手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
また、この義務化は、2024年4月1日以前に発生した相続にも適用されるため、過去の相続案件についても確認しておくことが重要です。
相続登記を迅速に行うことで、将来的なトラブルを防ぎ、不動産を円滑に管理することが可能になります。
そのため、相続が発生した際には早めに専門家へ相談し、適切な手続きを進めることが推奨されます。
相続において不動産を受け継いだ場合、名義変更(相続登記)は重要な手続きです。 相続した不動産の名義変更について、気になる方も多いのではないでしょうか。 本記事では、相続した不動産の名義変更について以下の点を中心にご紹介します! […]
不動産相続の名義変更は自分でできる?

不動産を相続した際の名義変更は、自分で手続きすることも可能です。
必要な書類や手続きの流れを調べて準備を整えれば、専門家に依頼しなくても対応できます。
インターネットには名義変更の手続き方法が詳しく解説されているサイトが多く、これらを参考にすることで、手続きの概要を把握することができます。
不動産相続手続きを自分で行うことについて気になる方も多いのではないでしょうか? 不動産の相続手続きを自分で行うためには、事前準備や必要書類を正確に把握することが重要です。 相続登記や税務手続きの流れを分かりやすく解説し、スムーズに手[…]
自分で不動産相続の名義変更を行う手順

相続する不動産の名義を確認
まず、法務局で登記事項証明書を取得し、不動産の現在の名義を確認します。
これは、過去の相続手続きが未完了で、名義が前の所有者のままになっていることがあるためです。
例えば、父親から不動産を相続したつもりで手続きを進めても、名義が祖父のままだった場合、そのままでは登記申請が受理されません。
最初に祖父から父親への名義変更を行う必要があるため、確認は欠かせません。
次に、登記事項証明書の取得方法について解説します。
登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取得可能です。
法務局に備え付けられている「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を貼付して提出します。
申請が完了すれば、その場で登記事項証明書を受け取ることができます。
費用は、不動産1件につき600円です。土地と建物の両方が対象の場合、それぞれに手数料が必要になるため、計1,200円かかります。
最後に名義変更の申請準備について解説します。登記事項証明書を取得したら、現在の名義や不動産情報に基づいて、必要書類を準備します。
これには、相続関係を証明する戸籍謄本や遺産分割協議書、固定資産評価証明書などが含まれます。
これらを元に、名義変更の登記申請書を作成します。
相続人の確定
不動産相続手続きを進める上で大切なのは、相続人の確定作業です。
被相続人(亡くなった方)の戸籍を調査して相続人を確認する必要があります。
被相続人の戸籍謄本を取得し、その記録を基に相続人を確定させます。
戸籍謄本は、被相続人の本籍地にある市区町村役場で取得が可能です。
相続人の範囲や相続の順序は民法で定められており、以下のような優先順位で決まります。
- 配偶者
配偶者は常に相続人
他の順位に関係なく、必ず相続の権利があります。
- 第1順位
子や孫(直系卑属)
配偶者と共に相続人となります。
- 第2順位
親や祖父母(直系尊属)
第1順位の相続人がいない場合に相続権が発生します。
- 第3順位
兄弟姉妹(傍系血族)
第1順位および第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。
被相続人に配偶者がいる場合は、常に相続人に含まれます。
また、配偶者がいない場合は、第1順位の子や孫が優先されますが、これらがいない場合には第2順位の親や祖父母が相続人となります。
さらに、第1順位と第2順位の相続人が存在しない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続権を持つことになります。
戸籍を調査して相続人を確定させることは、遺産分割や登記手続きを進める上で欠かせないステップです。
正確に相続人を確定させるためにも、必要な戸籍謄本をすべて揃え、記録をしっかり確認しましょう。
遺産分割協議書を完成させる
法定相続人が一人だけの場合、その相続人が遺産全てを引き継ぐことが可能です。
しかし、相続人が複数いる場合には、法定相続分に従って分割するのが一般的ですが、遺産の種類や内容によっては簡単に分割できないケースもあります。
このような場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、それぞれの相続分を話し合いで決定する必要があります。
遺産分割協議では、法定相続分に縛られることなく、各相続人の同意を得て柔軟に分配方法を決めることが可能です。
協議の結果、分割方法が決まった際には、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
この協議書には相続人全員の署名と実印による捺印が必要です。
また、印鑑証明書を添付し、税務署などの関係機関に提出します。
一方、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
調停でも解決できなかった場合には、裁判所の判断によって遺産の分割が行われることになります。
必要書類を取得
相続登記に必要な書類は非常に多岐にわたります。
相続人が複数いる場合には、各相続人の戸籍謄本を揃える必要があり、その手間は決して軽視できません。書類の種類や必要性については後ほど詳しく説明しますが、すべてを漏れなく準備することが重要です。
相続登記の手続きでは、基本的に「原本」の提出が求められます。
遺産分割協議書や遺言書、相続人全員の印鑑証明書なども例外ではなく、写しでは受け付けてもらえません。
ただし、同じ書類を相続税の申告や預貯金口座の解約など他の手続きで再利用する場合も多いため、何度も取り寄せる手間を省くためには「原本還付」という手続きが役立ちます。
この手続きを行えば、法務局に提出した原本を返却してもらえます。
以下に手順を説明します。
- 原本をコピーする
まず、原本を原寸サイズでコピーします。
必要な書類が複数ある場合は、それぞれ全てコピーしてください。
- 「原本と相違ない」旨を記載する
コピーした書類の余白に「この写しは原本と相違ありません」と明記し、署名と捺印をします。
この際、申請書で使用した印鑑と同じものを使用する必要があります。
複数の書類をまとめる場合は、最初のページに署名・捺印し、さらに綴じ目ごとに契印を行います。
- 法務局に書類を提出する
原本と原本還付申請書、そしてコピーを法務局へ提出します。
手続きが終了すると、通常10日ほどで原本が返却されます。
この原本還付を利用することで、他の手続きにも効率よく対応できるようになります。
手間を省き、スムーズに手続きを進めるために、この制度を活用することをお勧めします。
登記申請書を作成
登記申請書を作成する際は、相続の方法によって必要な書類や申請書の形式が異なるため、それに応じた準備が必要です。
例えば、遺産分割協議による相続、法定相続分による相続、遺贈による相続など、どの形態で相続が行われるかによって、必要書類が変わります。
これらの条件を正確に把握した上で、適切な書類を揃えましょう。
法務局のウェブサイトでは、具体的な申請書の様式や作成手順が詳しく解説されています。
「不動産登記の申請書様式」や「登記手続ハンドブック」といった資料を参考にすることで、必要な情報を確認しながら作業を進めることができます。
これらを活用することで、記載漏れや誤記入を防ぎ、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
正確な書類作成は、相続登記をスムーズに完了させるために重要なステップですので、公式の情報を確認しながら慎重に進めることをおすすめします。
法務局で申請
必要な書類が揃い、登記申請書の準備が整ったら、これらを法務局に提出します。
提出方法は以下の3つから選べます。
- 窓口での直接提出
管轄する法務局の窓口に直接足を運び、申請書類を提出する方法です。
担当者に不明点を確認できるため、書類の内容に自信がない場合にはおすすめです。
- 郵送での提出
郵便を利用して書類を法務局に送る方法です。送付前に、必要書類が全て揃っているかを念入りに確認し、トラブルを避けるために書留郵便や追跡可能な方法で送ると良いでしょう。
- オンライン申請
オンラインを利用した申請では、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。
ただし、戸籍謄本や住民票など一部の書類は、別途郵送または窓口での提出が必要となる場合があります。
完全にオンラインで完結するわけではないため、手続きの詳細を確認しておくことが重要です。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。
自身の状況に合った方法を選び、正確に提出することで、申請手続きをスムーズに進めましょう。
不動産相続の名義変更を自分で行うメリット

相続した不動産の名義変更を自分で行う最大の利点は、コストを抑えられることです。
専門家に依頼する場合、手続きにかかる費用に加えて報酬を支払う必要があり、依頼先によって料金は異なりますが、一般的には5万〜15万円程度が相場となっています。
一方、自分で名義変更の手続きを進めれば、必要な書類の取得費用や印紙代のみの負担で済みます。
その結果、費用を大幅に節約することが可能です。
不動産相続の名義変更を自分で行うデメリット
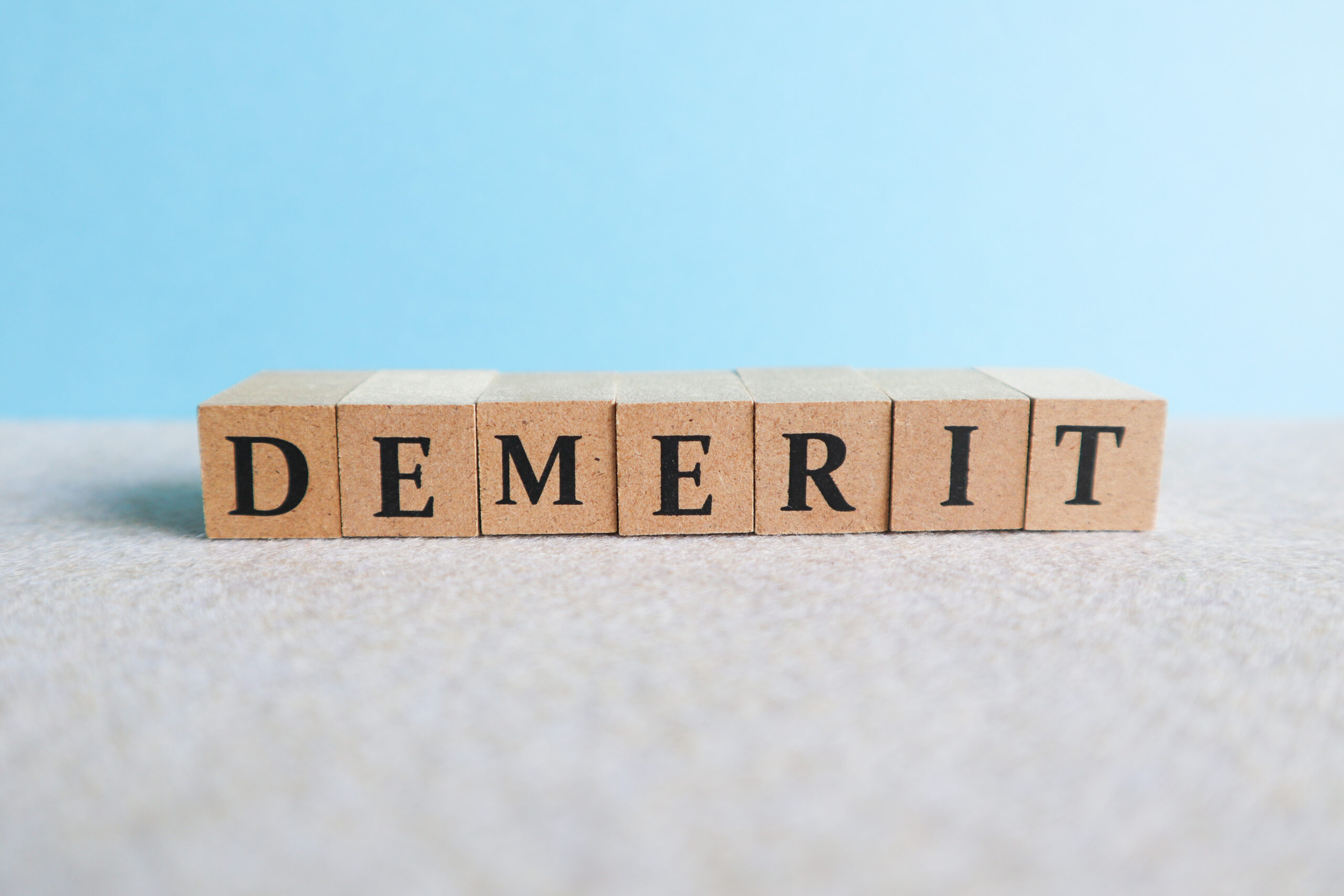
相続不動産の名義変更を自分で行うことは費用を抑えるメリットがありますが、それ以上にデメリットが多く、将来的なトラブルにつながる可能性もあります。以下に、自分で手続きを行う際の主なデメリットを3つ挙げます。
- 専門知識が必要になる
名義変更手続きを自力で進める場合、専門的な知識が不可欠です。不動産登記は一般的な日常生活では馴染みがなく、どのように進めるべきか分からない方も多いでしょう。
手続きを正確に行うためには、事前に民法や不動産登記法などを学ぶ必要があります。
これらの法律は内容が複雑で、初めて学ぶ人にとっては難解です。
さらに、自治体ごとに異なる手続き要件にも対応しなければならず、学習に割く時間や労力は非常に大きくなります。
- 手続きに多くの時間を要する
相続不動産の名義変更は、書類の準備や作成、法務局への申請など多くのステップがあり、時間を必要とします。
不備が見つかれば、そのたびに法務局や市役所などに出向くことになり、手続きがさらに長引く可能性があります。
公的機関の窓口対応は平日のみの場合が多いため、仕事や予定を調整しなければならない点も大きな負担です。
一方で、司法書士に依頼すれば、書類の作成や提出など多くの手続きが代行されるため、忙しい方にとって効率的な選択肢となります。
- 登記漏れのリスクが高い
名義変更を自分で行う場合、見落としや手続きの抜けが発生するリスクがあります。
例えば、実家が一戸建ての場合、家屋や土地だけでなく、付随する私道の所有権も登記が必要です。
しかし、被相続人自身が私道の所有を認識していなかったり、手続き時に見落としてしまったりすることが少なくありません。
不動産相続の名義変更にかかる費用は?

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算されます。
具体的には、評価額に0.4%を掛けた金額が登録免許税として必要です。
例えば、評価額が1,000万円の場合、4万円が登録免許税としてかかります。
固定資産税評価額は、不動産が所在する市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で発行される「固定資産評価証明書」に記載されています。
この評価証明書のコピーを登記申請時に提出する必要があります。
また、毎年送付される固定資産税の納税通知書にも評価額が記載されているため、そのコピーを代用することも可能です。
相続登記には必要な書類があり、それぞれ取得費用がかかります。
以下に詳しく解説します。
- 戸籍謄本
1通450円(現行の戸籍で効力があるもの)
- 除籍謄本
1通750円(既に閉じられた戸籍)
- 原戸籍謄本
1通750円(改正前の古い様式の戸籍)
- 住民票
1通300円
- 戸籍の附票
1通300円(戸籍に記載された住所履歴)
- 印鑑証明書
1通300円
相続登記に必要な費用は、物件の評価額や相続関係の複雑さによって変動するため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
遺産相続の控除額についてよくある質問

名義変更の司法書士費用はいくらくらいですか?
相続手続きの場合、報酬の相場はおおよそ6万〜10万円程度です。
一方、贈与手続きの場合は5万〜8万円が一般的とされています。
ただし、この金額は地域や手続きの複雑さ、必要な戸籍の数、不動産の件数や評価額など、具体的な状況によって変動します。
特に手続きが煩雑な場合や特殊な事情がある場合には、15万円以上の費用がかかることもあります。
不動産相続の名義変更の期限はいつまで?
不動産の名義変更は法律で義務付けられているわけではないため、手続きに明確な期限はありません。
しかし、長期間放置してしまうと、必要な書類の取得が難しくなる可能性があります。
さらに、将来的に法律の改正によって相続登記が義務化される可能性も指摘されています。
そのため、不動産を相続した際には、手続きを後回しにせず、早めに法務局で名義変更を完了させることをおすすめします。
不動産相続の名義変更についてのまとめ

ここまで不動産相続の名義変更についてお伝えしてきました。
不動産相続の名義変更が自分で行えるかについての要点をまとめると以下の通りです。
- 不動産相続に伴う名義変更は、不動産の所有者が亡くなった際に、その権利を相続人に引き継ぐために行う重要な手続き
- 不動産を相続した際の名義変更は、自分で手続きすることも可能で、必要な書類や手続きの流れを調べて準備を整えれば、専門家に依頼しなくても対応できる
- 不動産相続の名義変更の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算される
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



